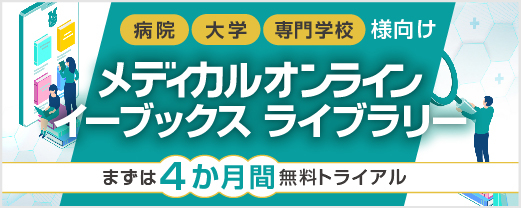| 書籍名 |
こんなときどうする? 在宅看護Q&A |
| 出版社 |
メディカ出版
|
| 発行日 |
2015-12-10 |
| 著者 |
|
| ISBN |
9784840454728 |
| ページ数 |
324 |
| 版刷巻号 |
電子版 |
| 分野 |
|
| 閲覧制限 |
未契約 |
在宅看護の「智」と「ノウハウ」を1冊に!在宅看護の対象は幅広く、経験のない患者を担当することも多い。そこで、訪問看護でよく遭遇する困ったケア場面を様々な切り口からQ&Aで取り上げ、ベテラン看護師ならどう解決するかノウハウをまとめた。訪問看護師だけでなく在宅に関わる病院看護師にも役立つ1冊。
目次
参考文献
総論 在宅看護で求められる知識と技術Q & A
P.17 掲載の参考文献
-
1) 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課. 薬局における麻薬管理マニュアル平成23年4月. <http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/dl/mayaku_kanri_02.pdf>, (2015-11-06).
-
2) 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課. 病院・診療所における麻薬管理マニュアル平成23年4月. <http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/dl/mayaku_kanri_01.pdf>, (2015-11-06).
P.20 掲載の参考文献
-
1) 東京大学医学部・大学院医学系研究科成人看護学/緩和ケア看護学分野. 「高齢者訪問看護質指標」を活用した訪問看護師応援サイト. <http://plaza.umin.ac.jp/houmonkango/>, (2015-11-06).
P.22 掲載の参考文献
-
1) 押川眞喜子編著. これだけは知っておきたい! 在宅での感染対策 : 訪問看護のための基本と実践. 日本看護協会出版会, 2008年, 108p.
P.26 掲載の参考文献
-
1) 厚生労働省医政局長. 在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取り扱いについて (平成17年3月24日). <http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/tankyuuin/index.files/ihouseisokyaku2zaitaku.pdf>, (2015-11-06).
P.35 掲載の参考文献
-
1) 日本老年医学会. 高齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイドライン. 人工的水分・栄養補給の導入を中心として (2012). <www.jpn-geriat-soc.or.jp/info/topics/pdf/jgs_ahn_gl_2012.pdf>, (2015-11-06).
P.37 掲載の参考文献
-
1) 厚生労働省. 平成25年介護サービス施設・事業所調査の概況. 5. 介護保険施設利用者の状況. <http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service13/index.html>, (2015-11-06).
-
2) 須田啓一. 介護老人保健施設における看取りの医学的分析. ホスピスケアと在宅ケア. 20 (1), 2012, 67-9.
-
3) 小野光美. 介護老人保健施設の看取りにおける看護管理者の実践内容. 日本看護倫理学会誌, 7 (1), 2015, 68-76.
P.39 掲載の参考文献
-
1) 中山和弘ほか編. 患者中心の意思決定支援 : 納得して決めるためのケア. 中央法規, 2012, 28-36.
P.44 掲載の参考文献
-
1) 厚生労働省. 終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン (2007). <http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/05/s0521-11.html>, (2015-11-06).
-
2) 日本老年医学会. 高齢者の摂食嚥下障害に対する人工的な水分・栄養補給法の導入をめぐる意思決定プロセスの整備とガイドライン作成 (2012). <http://www.jpn-geriat-soc.or.jp/josei/pdf/h22_jigyousaitaku.pdf> (2015-11-06).
-
3) 日本救急医学会. 救急医療における終末期医療に関する提言 (ガイドライン) について. (2007). <http://www.jaam.jp/html/info/2007/info-20071116.htm>, (2015-11-06).
-
4) 終末期における輸液治療に関するガイドライン編集委員会ほか. 終末期癌患者に対する輸液治療のガイドライン. <http://www.jspm.ne.jp/guidelines/glhyd/glhyd01.pdf>, (2015-11-06).
-
5) 千葉大学大学院看護学研究科. エンド・オブ・ライフケア看護学. <http://www.n.chiba-u.jp/eolc/opinion/>, (2015-11-06).
P.46 掲載の参考文献
-
1) 宇都宮宏子. "病院で行う在宅療養移行支援・退院支援・退院調整・外来支援". 看護がつながる在宅療養移行支援 : 病院・在宅の患者像別看護ケアのマネジメント. 宇都宮宏子, 山田雅子編. 日本看護協会出版会, 2014, 11.
P.49 掲載の参考文献
-
1) 大井玄. 「痴呆老人」は何をみているか. 新潮社, 2009, 223p.
-
2) 鈴木和子ほか. 家族看護学 : 理論と実践. 第4版. 日本看護協会出版会, 2012, 323p.
-
3) イヴ・ジネストほか : Humanitude : 老いと介護の画期的な書 . 本田美和子監修. 辻谷真一郎訳. トライアリスト東京, 2014, 438p.
P.52 掲載の参考文献
-
1) 片倉佐央里ほか. 子育て中のがん患者が子供に病気の説明をしていない理由について : 実態調査の質的分析. 日本緩和医療学会学術大会プログラム 抄録集. 17th, 2012, 318.
-
2) 小澤美和. がん患者と子どもに対する支援 : 親ががんであることを子どもに伝えるためのサポート (第2回) 子育て中のがん患者とその子どもの心. がん看護. 18 (3), 2013, 373-376.
-
3) American Cancer Society. Helping Children When a Family Member Has Cancer: Dealing With a Parent's Terminal Illness. <http://www.cancer.org>, (2015-11-06).
P.55 掲載の参考文献
-
1) 千葉大学大学院看護学研究科. エンド・オブ・ライフケア看護学. <http://www.n.chiba-u.jp/eolc/opinion/>, (2015-11-06).
各論 困ったケア場面Q & A
P.61 掲載の参考文献
-
1) 宮坂勝之編. 日本版PALSスタディガイド改訂版. 小児二次救命処置の基礎と実践. エルゼビア・ジャパン, 2013, 512p.
P.64 掲載の参考文献
-
1) 鈴木康之ほか監修. 写真でわかる重症心身障害児 (者) のケア. インターメディカ, 2015, 272p.
-
2) 浅野大喜. リハビリテーションのための発達科学入門. 協同医書出版社, 2012, 128p.
-
3) 玉川大学赤ちゃんラボ. なるほど! 赤ちゃん学. 新潮社, 2015, 222p.
P.70 掲載の参考文献
-
1) 馬場直子. こどもの皮膚診療アップデート. シービーアール, 2013, 2-3.
P.74 掲載の参考文献
-
1) 厚生労働省. 職場における腰痛予防の取組を! : 19年ぶりに「職場における腰痛予防対策指針」. <http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/youtsuushishin.html>, (2015-11-06).
P.77 掲載の参考文献
-
1) 西元寺秀明ほか. 気管切開後の気管 : 無名動脈瘻の1例. ICUとCCU. 3, 1979, 987-96.
P.80 掲載の参考文献
-
1) 厚生労働省. 母子健康手帳について. 省令様式. <http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/s2015.pdf>, (2015-11-06).
P.83 掲載の参考文献
-
1) 船戸正久ほか. 改訂2版 医療従事者と家族のための小児在宅医療支援マニュアル. メディカ出版, 2010, 111.
P.86 掲載の参考文献
-
1) Stmme, G, et al. Die fruhkindliche Bewegungsentwicklung. 2012, verlag selbstbestimmtes leben, 64.
-
2) Holtz, R. Therapie-und Alltagshilfen fur zerebralparetische Kinder. Pflaum, 2004, 113-5.
P.94 掲載の参考文献
-
1) 木下千鶴. NICUにおけるファミリーセンタードケア. 日本新生児看護学会誌. 8(1), 2001, 59-67.
P.96 掲載の参考文献
-
1) Olshansky, S. Chronic sorrow: A response to having a mentally defective child. Social Casework. 43, 1962, 190-3.
-
2) Lawrence, GC. et al. Posttraumatic Growth in Clinical Practice. Routledge, 2013, 184p.
-
3) 久野典子ほか. 在宅で重症心身障害時を養育する母親の養育負担感とそれに影響を与える要因. 日本看護研究学会雑誌. 29 (5), 2006.
-
4) 古田聡美. 訪問看護ステーションにおける小児訪問看護の実際 : 小児訪問看護の問題点. 鹿児島純心女子短期大学研究紀要. 38, 2008, 163-72.
P.99 掲載の参考文献
-
1) 廣川聖子ほか. 生活保護受給者自立支援事業における行政と民間との連携 : 今後の地域精神保健アウトリーチ支援に必要な技術に関する検討. 医療と社会, 22 (4), 2013, 343-57.
P.102 掲載の参考文献
-
1) チャールズ・A・ラップ. ストレングスモデル 第3版 : リカバリー志向の精神保健福祉サービス. 田中秀樹監訳, 金剛出版, 2014, 450p.
-
2) メアリー・エレン・コープランド. 元気回復行動プラン. 久野恵理訳, 道具箱, 2009, 95p.
P.104 掲載の参考文献
-
1) 姫井昭男. 精神科の薬がわかる本. 第3版. 医学書院, 2014, 38, 73.
-
2) 中井久夫. 看護のための精神医学. 第2版, 医学書院, 2005, 101-2.
P.106 掲載の参考文献
-
1) メアリー・エレン・コープランド. 元気回復行動プラン : WRAP. 久野恵理訳, 道具箱, 2009, 95p.
P.109 掲載の参考文献
-
1) ゲイル ・スティケティー. ホーディングへの適切な理解と対応 認知行動療法的アプローチセラピストガイド. 五十嵐透子訳. 金子書房, 2013, 193p.
P.111 掲載の参考文献
-
1) 姫井昭男. 精神科の薬がわかる本. 第3版. 医学書院, 2014, 38, 73.
P.113 掲載の参考文献
-
1) 日本精神保健福祉士協会監修. 精神保健福祉士まるごとガイド : 資格のとり方・しごとのすべて. 改訂版. ミネルヴァ書房, 2014, 125p.
P.115 掲載の参考文献
-
1) 小澤温監修, 埼玉県相談支援専門員協会編. 相談支援専門員のためのストレングスモデルに基づく障害者ケアマネジメントマニュアル : サービス等利用計画の質を高める. 中央法規出版, 2015, 4.
-
2) 厚生労働省. 障害のある人に対する相談支援について. <http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/soudan.html>, (2015-11-06).
P.117 掲載の参考文献
-
1) 萱間真美編. 精神看護. 第2版. 照林社, 2015, 435p (パーフェクト臨床実習ガイド).
P.119 掲載の参考文献
-
1) 公益財団法人日本訪問看護財団監修, 萱間真美ほか編. 精神科訪問看護 : Q&Aと事例でわかる訪問看護. 中央法規出版, 2015, 276p.
P.121 掲載の参考文献
-
1) 立岩真也. "呼吸器のこと" ALS不動の身体と息する機械. 医学書院, 2005, 152-62.
-
2) 川口有美子. "静まりゆく人" 逝かない身体 : ALS的日常を生きる. 医学書院, 2009, 96-8.
-
3) 厚生労働省. 終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン. <http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/05/dl/s0521-11a.pdf>, (2015-08-27).
P.123 掲載の参考文献
-
1) 立岩真也. "呼吸器のこと" ALS不動の身体と息する機械. 医学書院, 2005, 169-83.
-
2) 川口有美子. "静まりゆく人" 逝かない身体 : ALS的日常を生きる. 医学書院, 2009, 57-67.
P.126 掲載の参考文献
-
1) 日本神経学会. "告知, 診療チーム, 事前指示, 終末期ケア". 筋萎縮性側索硬化症診療ガイドライン2013. <http://www.neurology-jp.org/guidelinem/als2013_index.html>, (2015-10-14).
-
2) LIVE TODAY FOR TOMORROW プログラム委員会. ALS筋委縮性側索硬化症疾患の疾患・治療に関する情報プログラム. <http://www.als.gr.jp/>, (2015-08-28).
-
3) 自分らしい「生き」「死に」を考える会-あなたは終末期をどのように迎えたいですか? -. 私の生き方連絡ノート (意思表示カード). <http://www.ikisini.com/note.html>, (2015-08-28).
P.128 掲載の参考文献
-
1) 奈良勲ほか監修. "運動ニューロン疾患の筋萎縮性側索硬化症 (ALS)". 神経内科学. 第3版. 医学書院, 2010, 242-3, (標準理学療法学・作業療法学 専門基礎分野シリーズ).
-
2) 落合慈之ほか監修. "筋萎縮性側索硬化症 (ALS)". リハビリテーションビジュアルブック. 学研メディカル秀潤社, 2009, 48-53.
-
3) 難波玲子. ALSの在宅医療 : 在宅医療のとらえ方. JOURNAL OF CLINICAL REHABILITATION. 18 (9), 2009, 837-41.
P.131 掲載の参考文献
-
1) 立岩真也. "その先を生きる". ALS不動の身体と息する機械. 医学書院, 2005, 275-7.
-
2) 川口有美子. "発汗コミュニケーション". 逝 (い) かない身体 : ALS的日常を生きる. 医学書院, 2009, 184-6.
-
3) 日本ALS協会編. "コミュニケーションの問題". 新ALSケアブック : 筋萎縮性側索硬化症療養の手引き. 川島書店, 2006, 95-122.
P.136 掲載の参考文献
-
1) 倉田なおみほか. 簡易懸濁法Q&A part 1基礎編. 第2版. じほう, 2012, 200p.
-
2) 倉田なおみ. 内服薬 経管投与ハンドブック : 簡易懸濁法可能薬品一覧. 第2版. 藤島一郎監修. じほう, 2006, 462p.
P.145 掲載の参考文献
-
1) 前川厚子編著. 在宅医療と訪問看護・介護のコラボレーション. 改訂2版. オーム社, 2009, 93-4, 219-20.
-
2) 東京都医学総合研究所. 難病ケア看護データーベース. <http://nambyocare.jp/results/topics2/chap4-1.html>, (2015-8-31).
P.150 掲載の参考文献
-
1) 厚生労働省. 難病特別対策推進事業について (厚生労働省健康局長通知) 」. <http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000023og3-att/2r98520000023onv.pdf>, (2015-10-06).
-
2) 内閣府大臣官房政府広報室. 政府広報オンライン「暮らしのお役立ち情報『難病と小児慢性特定疾患にかかる医療費助成が変わりました! 』」. <http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201412/3.html>, (2015-10-06).
-
3) 厚生労働省. 難病対策. <http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/>, (2015-10-06).
-
4) 梅田麻希. "難病支援・障害支援". 系統看護学講座 専門基礎分野 健康支援と社会保障制度 公衆衛生. 第13版. 神馬征峰ほか編. 医学書院. 2015, 232-49.
P.153 掲載の参考文献
-
1) 3学会合同呼吸療法認定士認定委員会事務局. 3学会合同呼吸療法認定士認定制度10周年記念 : 第10回3学会合同呼吸療法認定士認定講習会テキスト. 2005.
-
2) 南雲秀子. 自己管理と生活指導 薬物療法と酸素療法を中心に. ナーシング・トゥデイ. 19 (8), 2004, 24-5.
P.156 掲載の参考文献
-
1) 厚生労働省. (社会福祉士及び介護福祉士法施行規則) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令 (厚生労働省第126号). <http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/dl/2-4-2.pdf>, (2015-08-17).
-
2) 公益財団法人日本訪問看護財団編著. "在宅での介護職員等による喀痰吸引等実施における連携イメージ" 介護職員等のための医療的ケア : 喀痰吸引・経管栄養等の研修テキスト. ミネルヴァ書房, 2013, 62.
P.159 掲載の参考文献
-
1) 駒瀬裕子監修. 明日からできる実践吸入指導. 改訂第2版. メディカルレビュー社, 2015, 144p.
-
2) リウマチ・アレルギー情報センター. ガイドライン 成人気管支喘息. <http://www.allergy.go.jp/allergy/guideline/02/index.html>, (2015-08-13).
-
3) 成人気管支喘息診療のミニマムエッセンス作成ワーキンググループ編. 表8. 喘息発作の強度に対応した管理のポイント. 成人気管支喘息診療のミニマムエッセンス. <http://dl.med.or.jp/dl-med/chiiki/allergy/bronchial_asthma.pdf>, (2015-08-13).
P.162 掲載の参考文献
-
1) 篠田道子. 多職種連携を高めるチームマネジメントの知識とスキル. 医学書院. 2011, 128p.
P.164 掲載の参考文献
-
1) 日本循環器学会. 冠攣縮性狭心症の診断と治療に関するガイドライン (2013年改訂版). <http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2013_ogawah_h.pdf>, (2015-06-28).
-
2) 医学情報研究所編. 病気が見えるvol. 2 : 循環器. 第3版. メディックメディア, 2013, 344p.
P.166 掲載の参考文献
-
1) 山村恵子監修. ワーファリン患者様の日常生活の注意点. エーザイ. <http://www.eisai.jp/medical/products/warfarin/cautions/>, (2015-06-28).
-
2) ワーファリン添付文書. エーザイ. <http://database.japic.or.jp/pdf/newPINS/00050032.pdf>, (2015-06-28).
-
3) Kudou, T. Warfarin antagonism of natto and increase in serum vitamin K by intake of natto. Artery. 17 (4), 1990, 189-201.
-
4) 鈴木正彦. 薬理学. 改定第3版. 医学芸術新社, 2010, 231p, (新クイックマスター).
-
5) 日本循環器学会. 慢性心不全治療ガイドライン (2010年改訂版). <http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2010_matsuzaki_h.pdf>, (2015-07-20).
-
6) 医学情報研究所編. 病気が見えるvol. 2 : 循環器. 第3版. メディックメディア, 2013, 344p.
P.172 掲載の参考文献
-
1) 日本糖尿病療養指導士認定機構編著. "IX章 合併症・並存疾患の治療・療養指導". 日本糖尿病療養指導ガイドブック2015. メディカルレビュー社, 2015, 158-84.
-
2) 日本糖尿病教育・看護学会編. "フットケアのためのアセスメント". 糖尿病看護フットケア技術. 第3版. 日本看護協会出版会, 2014, 44-95.
P.178 掲載の参考文献
-
1) 正野逸子ほか編著. "インスリン". 看護実践のための根拠がわかる在宅看護技術. メヂカルフレンド社, 2015, 282-95.
-
2) 正野逸子ほか編著. "腹膜透析". 看護実践のための根拠がわかる在宅看護技術. メヂカルフレンド社, 2015, 269-81.
-
3) 角田直枝編. "インスリン". 知識が身につく! 実践できる! よくわかる在宅看護. 学研メディカル秀潤社, 2012, 191-9.
-
4) 角田直枝編. "腹膜透析". 知識が身につく! 実践できる! よくわかる在宅看護. 学研メディカル秀潤社, 2012, 200-9.
-
5) 川野良子ほか編. "腹膜透析". 透析看護ケアマニュアル. 中山書店, 2014, 178-250.
-
6) 佐藤エキ子. "腹膜透析". 写真でわかる透析看護 : 透析患者のQOL向上を目指すケア. インターメディカ, 2008, 61-110.
-
7) 日本透析学会. 腹膜透析ガイドライン2009年版. 日本透析学会雑誌. 42 (4), 2009, 289-94.
-
8) 古川裕之ほか編. "主な生活習慣病に使用する薬 : 8 糖尿病". 疾病の成り立ち (2) 臨床薬理学. メディカ出版, 2013, 47-50 (ナーシンググラフィカ).
-
9) テルモ株式会社. CAPD : 日本のPD療法の普及と発展をめざして. <http://capd.terumo.co.jp/>, (2015-10-09).
-
10) バクスター株式会社. 腎臓病・腹膜透析 (PD). <http://www.baxter.co.jp/patient/kidney/>, (2015-10-09).
P.181 掲載の参考文献
-
1) 小山珠美ほか. "接触嚥下障害のある患者への在宅療養移行支援". 看護がつながる在宅療養移行支援. 宇都宮宏子ほか編. 日本看護協会出版会, 2014, 134-56.
P.184 掲載の参考文献
-
1) 藤野智子. "22の場面で知る急変対応 : 脳内出血". 場面別どう見る! どう動く! 緊急対応マニュアル. 佐藤憲明編. 照林社, 2010, 32-9.
-
2) 佐藤憲明. "22の場面で知る急変対応 : 脳梗塞". 場面別どう見る! どう動く! 緊急対応マニュアル. 佐藤憲明編. 照林社, 2010, 40-7.
-
3) 丹羽由美子. "意識障害=頭蓋内病変と思い込まない! ". 「何か変? 」を見逃さない急変アセスメント. 佐藤憲明編. 照林社, 2015, 104-9.
-
4) 直井みつえ. "原因不明の意識障害では, 電解質異常も疑いたい! ". 「何か変? 」を見逃さない急変アセスメント. 佐藤憲明編. 照林社, 2015, 110-6.
-
5) 佐々木勝教監修. "症例02 意識障害". ゼロからわかる救急・急変看護. 成美堂出版, 2013, 36-45.
P.187 掲載の参考文献
-
1) 緩和医療学会. がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン 2010年版. <http://www.jspm.ne.jp/guidelines/pain/2010/chapter02/02_02_02.php>, (2015-11-06).
-
2) 日本呼吸器学会. COPD (慢性閉塞性肺疾患) 診断と治療のためのガイドライン第2版 (2004). <http://www.internationalcopd.org/documents/Japanese/JRSGuidelinesJapan.pdf>, (2015-11-06).
P.192 掲載の参考文献
-
1) 厚生労働省. 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について. <http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/7-2.pdf>, (2015-11-06).
-
2) 厚生労働省. 平成27年度介護報酬改定の骨子. <http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000081007.pdf>, (2015-11-06).
P.196 掲載の参考文献
-
1) 千野直一編著. 現代リハビリテーション医学. 改定第3版. 金原出版, 2009, 494.
-
2) 鈴木和子ほか. 家族看護学 : 理論と実践. 第4版. 看護協会出版会, 2014, 336p.
-
3) 島崎寛将. 緩和ケアが主体となる時期のがんのリハビリテーション. 中山書店, 2014, 288p.
P.203 掲載の参考文献
-
1) 日本ヒューマン・ナーシング研究学会編著. 意識障害・寝たきり〔廃用症候群〕患者への生活行動回復看護技術 (NICD) 教本. メディカ出版, 2015, 204p.
P.207 掲載の参考文献
-
1) 奥野茂代ほか編. 老年看護学 : 概論と看護の実践. 第5版. ヌーヴェルヒロカワ, 2014, 500p.
-
2) 藤島一郎ほか著. 「摂食・嚥下状況のレベル評価」簡便な摂食・嚥下評価尺度の開発. リハビリテーション医学, 2006, 43, S249.
P.223 掲載の参考文献
-
1) 庄司広和. "2 がん薬物療法の基本概念". がん診療レジデントマニュアル. 国立がん研究センター内科レジデント編. 第6版, 医学書院, 2013, 20.
-
2) Common Toxicity Criteria,Version2.0 Publish Date April 30,1999. JCOG ホームページ <http://www.jcog.jp>, (2015-11-06).
P.228 掲載の参考文献
-
1) 日本がん看護学会ほか編. がん薬物療法における曝露対策合同ガイドライン 2015年版. 金原出版, 2015, 112p.
-
2) 市川智里ほか. 曝露を防ぐ日常手技 薬剤 抗がん薬取り扱い時の曝露対策 こんなときどうする? . Expert Nurse. 31 (9), 2015, 62-67.
-
3) 岩本寿美代ほか. 曝露を防ぐ日常手技 看護ケア 日常ケアでの曝露対策 こんなときどうする? . Expert Nurse. 31 (9), 2015, 68-73.
P.229 掲載の参考文献
-
1) 川越厚. がん患者の在宅ホスピスケア. 医学書院, 2013, 41.
P.233 掲載の参考文献
-
1) 新海哲. 総論 ナースが最低限押さえておきたい「オンコロジーエマージェンシー」の知識. プロフェッショナルがんナーシング. 4 (5), 2014, 70-1.
-
2) 国立がん研究センター内科レジデント編. がん診療レジデントマニュアル. 第6版. 医学書院, 2015, 528p.
-
3) 小島操子監訳. がん看護コアカリキュラム. 医学書院, 2007, 816p.
P.237 掲載の参考文献
-
1) 川越厚. がん患者の在宅ホスピスケア. 医学書院, 2013, 176p.
P.244 掲載の参考文献
-
1) 本田晶子. 在宅緩和ケア 訪問看護の現場から : 事例を通して伝えたいこと (第4回) 在宅における痛みの緩和. がん看護, 19(5), 2014, 501-3.
-
2) 特定非営利活動法人 日本緩和医療学会編. がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン. 金原出版, 2014, 45-7.
P.247 掲載の参考文献
-
1) 特定非営利活動法人日本緩和医療学会 緩和医療ガイドライン作成委員会編. がん患者の呼吸器症状の緩和に関するガイドライン 2011年版. 金原出版, 2011, 112p.
-
2) 川越厚. がん患者の在宅ホスピスケア. 医学書院, 2013. 176p.
P.252 掲載の参考文献
-
1) 日本緩和医療学会編. がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン 2014年版. 金原出版, 2014, 344p.
P.255 掲載の参考文献
-
1) 川越厚. がん患者の在宅ホスピスケア. 医学書院. 2013. 176p.
P.263 掲載の参考文献
-
1) 日本神経学会監修. 認知症疾患治療ガイドライン 2010 : コンパクト版 2012. 医学書院, 2012, 256p.
P.268 掲載の参考文献
-
1) 厚生労働省. 世界保健機関による国際疾病分類第10版 (ICD-10). <URL http://www.mhlw.go.jp/toukei/sippei/>, (2015-10-26).
P.270 掲載の参考文献
-
1) 高齢者尿失禁ガイドライン. <http://www.ncgg.go.jp/hospital/iryokankei/documents/guidelines.pdf>, (2015-10-26).
P.274 掲載の参考文献
-
1) 厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」. 身体拘束ゼロへの手引き : 高齢者ケアに関わるすべての人に. 2001, 82p.
P.278 掲載の参考文献
-
1) 高齢者権利擁護研究会編集. Q&A 高齢者の生活・介護支援の手引. 新日本法規出版, 2000, 2400p.
P.286 掲載の参考文献
-
1) 日本老年医学会編. 健康長寿診療ハンドブック : 実地医家のための老年医学のエッセンス. メジカルビュー社, 2011, 160p.
P.295 掲載の参考文献
-
1) 公益社団法人日本薬剤師会. 平成19年度老人保健事業推進費等補助金「後期高齢者の服薬における問題と薬剤師の在宅患者訪問薬剤管理指導ならびに居宅療養管理指導の効果に関する調査研究」. <http://www.nichiyaku.or.jp/action/wp-ontent/uploads/2008/06/19kourei_hukuyaku1.pdf>, (2015-11-06).
-
2) 日本老年医学会. 高齢者の安全な薬物療法ガイドライン 2015 (案). <http://www.jpngeriat-soc.or.jp/info/topics/pdf/20150401_01_01.pdf>, (2015-09-01).
P.302 掲載の参考文献
-
1) 押川真喜子編. 症例から学ぶ訪問看護の実際. 医薬ジャーナル社, 2008, 152-74.
-
2) 季羽倭文子監修. プロセスで理解する訪問看護のアセスメント (下) : がん・ターミナルケアの基礎知識と訪問看護過程. 中央法規出版, 2003, 10-20, 70-6.
P.309 掲載の参考文献
-
1) 川越博美ほか総編集. 訪問看護テキストステップ1-(2). 第1版. 日本看護協会出版会, 2011, 8-11, 343-54, 377-8.
-
2) 季羽倭文子監修 : プロセスで理解する訪問看護のアセスメント (下) : がん・ターミナルケアの基礎知識と訪問看護過程. 中央法規出版, 2003. 10-21, 70-6.
-
3) 押川真喜子編. 症例から学ぶ訪問看護の実際. 医薬ジャーナル社, 2008, 121-5, 152-6.
-
4) 清水哲郎ほか. 高齢者ケアと人工栄養を考える : 本人・家族の選択のために. 勇美記念財団2010年在宅医療助成事業, 2011, 20-38.
P.312 掲載の参考文献
-
1) 鈴木陽一. "疾病からみた退院支援の現状と問題点 : 2) 嚥下性肺炎, 特に気切患者の退院支援". Geriatric Medicine, 47 (3), 2009, 311-5.
-
2) 植田耕一郎ほか. 摂食・嚥下障害の評価 (簡易版) : 日本摂食・嚥下障害リハビリテーション学会医療検討委員会案. 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会雑誌, 15 (1), 2011, 96-101.
-
3) 川越博美ほか総編集. 訪問看護テキストステップ1-(2). 第1版. 日本看護協会出版会, 2011, 349-54, 376-8.
-
4) 岡本充子ほか編. 高齢者看護すぐに実践トータルナビ : 成人看護とはここがちがう! おさえておきたい身体機能の変化と慢性疾患. メディカ出版, 2013, 88-108.
-
5) 下田妙子. 高齢者の栄養管理ガイドブック : 高齢者福祉施設・病院・在宅などで役立つ お年寄りの栄養ケアマネジメントを適切に行うために. 文光堂, 2011, 10-27.
P.316 掲載の参考文献
-
1) 谷本真理子. アドバンス・ケア・プランニングとは? : 患者にとっての最善を考える. ナーシング・トゥデイ, 28 (3), 2013, 32-7.
-
2) 小野若菜子. ハワイ州におけるPalliative care, Hospice care, Bereavementcare の特徴. 聖路加看護大学紀要. 40, 2014, 54-9.
P.322 掲載の参考文献
-
1) 小野若菜子 "死別後のグリーフケア". 在宅ケア学第1巻 在宅ケア学の基本的考え方. 日本在宅ケア学会編. ワールドプランニング, 2015, 104-8.
-
2) 小野若菜子. "家族介護者に対して訪問看護師が行うグリーフケアとアウトカムの構成概念の検討". 日本看護科学会誌, 31 (1), 2011, 25-35.