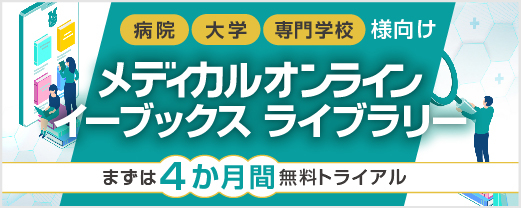| 書籍名 |
ナースの精神医学 改訂5版 |
| 出版社 |
中外医学社
|
| 発行日 |
2019-01-30 |
| 著者 |
- 上島国利(編著)
- 渡辺雅幸(編著)
- 榊惠子(編著)
|
| ISBN |
9784498175020 |
| ページ数 |
435 |
| 版刷巻号 |
5版1刷 |
| 分野 |
|
| 閲覧制限 |
未契約 |
ナースおよびコメディカルスタッフに必要な、これだけは知っておくべき精神医学の基本的な知識を簡潔且つ分かりやすく解説したテキスト。精神障害の概念と、症状・経過などの現象、検査・診断治療などの実際から、リハビリテーション、精神保健などまでを網羅した幅広い内容となっている。最新版では特に進展が著しい薬物療法や法律、社会でトピックとなっている項目について、最新の情報を反映。より充実した1冊となっている。
目次
- 表紙
- 執筆者
- 5版の序
- 初版の序
- 目次
- [1. 総論]
- [1] 精神医学, 精神医療とは
- 1. 精神の健康
- 2. 精神障害の概念
- 3. 精神医学・医療の歴史
- a. 欧米における精神医療の歴史
- b. 日本における精神医療の歴史
- [2] 精神障害の病因・分類
- [3] 診断と検査
- A. 精神科診療の特徴
- 1. 治療者 - 患者関係
- 2. 治療契約
- 3. インフォームド・コンセント
- B. 精神科的診察
- 1. 病歴聴取
- a. 現病歴
- b. 家族歴
- c. 生活歴, 生育歴, 教育歴および一般的背景
- d. 性格
- e. 既往歴, 合併症
- 2. 現症の把握
- 3. 表情, ふるまい, しぐさ ( 観察所見 )
- C. 身体的検査
- 1. 内科学的身体所見
- 2. 一般内科的検査
- 3. 神経学的検査
- D. 心理検査
- 1. 知能検査
- a. ビネー検査法
- b. ウェクスラー式知能検査
- c. コース立法体組み合わせテスト
- d. 老人用知能検査
- 2. 認知機能検査
- 3. 性格検査 / 人格検査
- a. 投影法検査
- b. 質問紙法
- c. 作業検査法 : 内田・クレペリン精神作業検査
- 4. テスト・バッテリー
- [4] 精神症状の把握
- A. 知覚の障害
- 1. 錯覚
- 2. 幻覚
- a. 幻視
- b. 幻聴
- c. 幻嗅
- d. 幻味
- e. 幻触
- f. 体感幻覚
- g. 幻 ( 影 ) 肢
- 3. その他の知覚障害
- B. 思考の障害
- 1. 思考の進み方の異常
- a. 観念奔逸
- b. 思考制止
- c. 迂遠
- d. 保続
- e. 思考途絶
- f. 思考滅裂
- 2. 思考体験の異常
- a. 思考の被影響 - 作為体験
- b. 強迫観念
- c. 恐怖 ( 症 )
- d. 支配観念
- 3. 思考内容の障害 : 妄想
- a. 妄想の生じ方による分類
- b. 妄想の内容による分類
- C. 自我意識の障害
- 1. 離人症
- 2. 被影響体験, 作為体験
- 3. 憑依妄想
- 4. 多重人格障害
- D. 感情の障害
- 1. 不安
- 2. 抑うつ
- 3. 気分高揚
- 4. 上機嫌 ( 多幸 )
- 5. 感情失禁
- 6. 感情鈍麻
- E. 意欲・行動の障害
- 1. 精神運動興奮
- 2. 精神運動制止
- 3. 昏迷
- 4. 個々の欲動の障害
- a. 食欲の異常
- b. 性欲の異常
- c. 自殺念慮, 自殺企図
- F. 意識障害
- G. 知能の障害
- 1. 精神遅滞
- 2. 認知症
- a. 診断基準
- b. 評価
- c. 類型化
- d. 脳血管性認知症
- e. 治療可能な認知症
- 3. 仮性認知症
- 4. 軽度認知障害
- H. 記憶の障害
- 1. 記銘力障害
- 2. 健忘
- 3. 見当識障害
- 4. コルサコフ症候群
- I. 病識の障害
- a. アントン症候群
- b. 疾病無認知
- c. コルサコフ症候群
- d. 幻覚が非現実であることの認識
- e. 統合失調症における病識
- f. 躁うつ病における病識
- [5] 脳科学と精神医学
- 1. 神経伝達物質と精神機能
- a. 神経細胞の構造と機能
- b. 向精神薬の作用と精神障害の病態
- 2. 免疫機能と精神機能
- a. 精神神経系 ( 脳 ) - 内分泌系とホメオスタシスならびにストレスとの関係
- b. うつ病と内分泌系
- c. 免疫系の精神神経系 ( 脳 ) および内分泌系への作用
- d. サイコオンコロジー ( 精神腫瘍学 )
- 3. 睡眠と概日リズム
- a. 睡眠および概日リズムとは何か
- b. 睡眠を生じるメカニズム
- c. 睡眠と精神医学的問題
- 4. 脆弱性 - ストレスモデル
- [6] 神経心理学
- 1. 大脳半球の優位性
- 2. 失語
- a. 失語症
- b. 失語症のリハビリテーションの看護上のポイント
- 3. 失認
- a. 物体失認
- b. 相貌失認
- c. 視空間失認
- d. 身体失認
- 4. 失行
- a. 肢節運動失行
- b. 観念運動失行
- c. 観念失行
- d. 構成失行
- e. 着衣失行
- 5. 脳局在症候群
- [2. 各論]
- [1] 内因性精神障害
- A. 統合失調症
- 1. 概念と歴史
- 2. 疫学
- 3. 成因
- a. 発病に関係する因子
- b. 脳内の生化学的変化と大脳の構造的特徴
- c. 症状悪化や再発に影響する要因
- 4. 症状
- 5. 病型
- 6. 経過と予後
- 7. 治療
- a. 薬物療法
- b. 精神療法 ( 心理的治療 )
- c. 精神科的リハビリテーション
- d. その他の特殊療法
- B. 統合失調症の類縁疾患
- a. 妄想性障害
- b. 非定型精神病
- c. 統合失調型障害
- C. 気分障害
- 1. 概念
- 2. 病因
- a. モノアミン仮説
- b. 神経伝達物質受容体仮説
- c. モノアミン以外による病態説
- 3. 病前性格
- 4. 症状
- 5. 鑑別疾患
- 6. 治療
- [2] 心因性精神障害
- A. 神経症とストレス関連障害
- 1. 概念, 病因, 治療
- 2. 各論
- a. 不安症群 / 不安障害群
- b. 強迫症および関連症群 / 強迫性障害および関連障害群
- c. 心的外傷およびストレス因関連障害群
- d. 身体症状症および関連症群
- e. 解離症群 / 解離性障害群
- f. その他の神経症
- B. 心身症
- 1. 心身症
- 2. 心身症の定義
- 3. 心身医学
- 4. 主な心身症
- 5. ICD - 10の分類
- 6. DSM - 5の分類
- 7. 心身症の診断
- 8. 心身症の治療
- 9. 各種の心身医学的治療
- a. 自律訓練法
- b. 筋弛緩法
- c. 交流分析
- d. ゲシュタルト療法
- e. 行動療法
- f. 認知療法
- g. バイオフィードバック療法
- 10. 東洋医学的治療
- a. 絶食療法
- b. 森田療法
- c. 内観療法
- d. ヨーガ療法
- 11. 摂食障害
- 12. 過換気症候群
- [3] 身体因性精神障害
- A. 器質性精神障害および症状性精神障害
- 1. 疾患の概念
- 2. 原因
- 3. 臨床症状
- a. せん妄
- b. 器質性健忘症候群
- c. 器質性気分障害
- d. 器質性統合失調症様障害
- e. 器質性パーソナリティ ( 人格 ) 障害
- 4. 各論
- 5. 診断と治療
- a. 原因疾患と精神症状の把握
- b. 治療歴の聴取
- c. 環境の整備
- d. 精神科薬物療法
- B. 物質依存, ギャンブル障害 ( 病的賭博 )
- 1. 物質依存
- a. 概念
- b. 病因
- c. 症状
- d. 診断
- e. 治療
- 2. ギャンブル障害 ( 病的賭博 )
- a. 概念
- b. 病因
- c. 診断
- d. 症状
- e. 治療
- C. てんかん
- 1. 概念
- 2. 原因
- 3. 分類
- 4. 症状
- 5. 治療
- [4] 老年期精神障害
- A. 器質性精神障害
- 1. 定義
- 2. 症状
- 3. 原因疾患と分類
- a. アルツハイマー型認知症
- b. レビー小体型認知症
- c. 前頭側頭型認知症
- d. 血管性認知症
- B. 機能性精神障害
- [5] 知的障害
- [6] 児童・青年期精神医学
- A. 心理発達の障害
- 1. 自閉スペクトラム症 / 自閉症スペクトラム障害
- B. 行為および情緒の障害
- 1. 注意欠如・多動症 / 注意欠如・多動性障害
- 2. 素行症 / 素行障害
- 3. チック症 / チック障害
- 4. 抜毛症
- 5. 選択性緘黙
- C. 思春期・青年期に特有な精神医学的問題
- 1. 不登校・ひきこもり
- 2. いじめ
- a. 概念
- b. 最近のいじめの特徴
- c. 大人は何をすべきか
- 3. 家庭内暴力
- [7] パーソナリティ障害
- 1. 概念
- 2. 病因
- 3. 分類
- a. クレッチマーの分類
- b. 「精神疾患の診断・統計マニュアル第5版 ( DSM - 5) 」 ( 2013 ) による分類
- 4. 治療
- [8] 睡眠障害
- 1. 不眠
- 2. 過眠
- 3. 睡眠 - 覚醒スケジュール障害
- 4. 睡眠時随伴症
- a. 夜驚症
- b. 睡眠時遊行症
- c. レム睡眠行動異常
- d. 悪夢
- [9] 性をめぐる問題
- 1. 概念
- 2. 病因
- 3. 分類
- a. 性別違和 ( 性同一性障害 )
- b. 性機能不全
- c. パラフィリア障害 ( 性倒錯 )
- 4. 治療
- [10] リエゾン精神医学
- 1. 概念と現況
- 2. 精神科リエゾン診療で扱う代表的な疾患・症状
- a. ICUや一般病棟にて : せん妄, 興奮
- b. 救急室, 救命救急センターにて : 自殺未遂
- c. がん患者の精神症状 : 正常範囲の反応と病的な症状
- d. 各種身体疾患と精神症状
- 3. 精神科リエゾン診療の実際
- [3. 治療と予防]
- [1] 精神療法 ( 心理療法 )
- A. 精神療法とは
- B. 精神分析療法 / 精神分析的精神療法
- 1. 理論
- a. こころの構造と相互作用
- b. こころの発達 : フロイトの心理性的発達理論
- 2. 方法
- C. 来談者中心療法
- D. 森田療法
- E. 内観療法
- F. 認知行動療法
- 1. 認知行動療法とは
- 2. 認知行動理論 ( 認知行動モデル )
- 3. 認知の2つのレベル
- 4. 認知のアンバランス ( 歪み )
- 5. 協同関係
- 6. 認知行動療法の進め方
- 7. 認知行動療法の技法
- G. 自律訓練法
- 1. 具体的な実施手順
- 2. 自律訓練法の効果と適用領域
- H. 催眠療法
- I. 遊戯療法
- J. サイコドラマ
- K. グループワーク, 集団療法
- 1. グループ / 集団の意味
- 2. 集団精神療法とは ?
- 3. 集団精神療法の実際
- a. コミュニティミーティング
- b. 小集団精神療法
- 4. 集団精神療法的なグループワークの様々
- L. 芸術療法
- 1. 芸術療法とは
- 2. 芸術療法の実際
- a. ダンス / ムーブメントセラピー
- b. ミュージックセラピー
- c. アートセラピー
- [2] 薬物療法
- 1. 向精神薬
- 2. 抗精神病薬
- a. 臨床効果
- b. 抗精神病薬の種類
- c. 抗精神病薬治療の特徴
- d. 抗精神病薬の副作用
- e. 抗精神病薬の生化学的作用メカニズム
- 3. 抗うつ薬
- a. 抗うつ薬の臨床効果
- b. 抗うつ薬の種類
- c. 抗うつ薬の作用機序と, 抗うつ効果や副作用との関連
- d. 抗うつ薬治療の特徴
- 4. 気分安定薬
- a. 気分安定薬の臨床効果
- b. 気分安定薬の種類
- c. 気分安定薬治療の特徴
- 5. 抗不安薬
- a. 抗不安薬の臨床効果
- b. 抗不安薬の作用機序
- c. 抗不安薬の副作用
- 6. 睡眠薬
- a. 睡眠薬とは
- b. ベンゾジアゼピン系睡眠薬の種類
- c. 副作用
- 7. 抗てんかん薬
- 8. 精神刺激薬 ( 覚せい剤 ) と関連薬
- 9. 抗酒薬
- 10. 抗認知症薬
- [3] 電気けいれん療法
- 1. 電気けいれん療法とは
- 2. 適応
- 3. 旧来型ECT施行の実際 - 特に看護との関連において -
- 4. 修正型ECTについて
- 5. 反復経頭蓋磁気刺激法
- [4] 精神科リハビリテーション
- A. 精神障害者リハビリテーションの歴史と概念
- 1. 精神障害者リハビリテーションの概念と特徴
- a. リハビリテーションと社会復帰
- b. 精神障害者リハビリテーションと支持的環境
- 2. 精神障害者リハビリテーションの歴史
- a. モラル療法と人権擁護
- b. 環境療法と治療共同体
- c. 施設病と全体施設
- d. 日本の精神障害者リハビリテーション
- e. レジリエンスとストレングス
- f. 当事者中心の動き
- 3. 精神障害者リハビリテーションと国際生活機能分類
- a. 国際障害分類
- b. 国際生活機能分類と精神障害者リハビリテーション
- c. ICFと生活機能
- 4. 脱施設化とコミュニティケア
- a. 世界の精神病床数の変化と日本の脱施設化の遅れ
- b. 精神障害者の退院支援とコミュニティ・ケア
- c. 精神障害者リハビリテーションと精神保健福祉の今後
- B. 環境療法 ( 社会療法 )
- 1. 環境療法 ( 社会療法 ) とは
- 2. 作業療法とは
- a. 「伝統的な作業療法」と新たな「作業療法Occupational Therapy」
- b. 環境と作業療法
- 3. 社会療法とは
- 4. 人的環境としてのスタッフ ( 医療保健福祉従事者 )
- C. 家族療法
- 1. システムとしての家族
- a. ダブルバインド
- b. 偽相互性と偽敵対性
- c. 紛らかす
- d. 一般システム理論
- e. 家族成員の役割とIP
- 2. 円環的因果関係
- 3. 家族と感情表出
- 4. 家族関係と個人の自己分化度
- 5. 家族の多世代的理解
- 6. 物語としての家族
- 7. 家族の対処能力とサポート
- 8. 家族療法の理論の発展
- D. 地域生活支援
- 1. 地域生活をサポートするサービス ( 地域生活支援サービス )
- 2. 医療
- a. ACT
- b. 精神科デイケア
- c. オープンダイアローグ
- 3. 精神科訪問看護
- a. 精神科訪問看護の概要
- b. 訪問看護における基本的心構え
- c. 精神科訪問看護の具体的内容
- E. 当事者活動とピアサポート
- 1. 当事者活動
- 2. ピアサポート
- 3. ピアサポートの効果
- 4. ピアサポートの提供される形
- a. セルフヘルプグループ ( 自助グループ )
- b. 疾患や障害を経験した人がピアサポートを提供する人として雇用される
- 5. 医療者の関わり
- [5] 自殺対策
- A. 自殺の危険因子
- 1. 自殺未遂歴
- a. 選ばれた手段の致死性
- b. 自殺未遂直後の感情
- 2. 精神疾患
- 3. サポートの不足
- 4. 性別
- 5. 年齢
- 6. 喪失体験
- 7. 他者の死の影響
- 8. 事故傾性
- 9. 虐待
- B. 自殺の危険の高い患者への対応の原則
- C. 演習
- [4. 精神保健看護]
- [1] 精神科看護の特徴
- A. 精神医学と看護ケア
- 1. 精神医学の知識
- 2. 個別看護の知識
- 3. 精神医学と看護ケアの接点
- [2] 精神保健とライフサイクル
- A. 精神保健と危機
- 1. ストレスと危機
- a. ストレスの定義
- b. ストレスの種類
- c. ストレスによる反応 ( セリエによる一般適応症候群の段階 )
- d. ストレスへの対処
- e. 危機の定義
- f. 危機の種類
- g. 危機の特徴
- h. 危機への対処
- 2. ライフサイクルと危機
- a. ライフサイクル ( 人生周期 )
- b. エリクソンの漸成的発達論
- c. 危機を乗り越える力
- B. 死にゆく人とケア
- 1. 死にゆく人の理解
- a. 全人的苦痛の理解
- b. 死にゆく人の心理的プロセス
- c. 老いの先に迎える死
- 2. 死にゆく人へのケア
- a. 患者の体験に寄り添い続ける
- b. 患者の意思決定を支援する
- c. 今を生きることを支える
- d. 家族へのケア
- 3. 患者の死を悼み, 専門職としてケアを振り返る
- C. 学校のメンタルヘルス
- 1. 学校とは何か
- 2. 学校をめぐるメンタルヘルスの状況
- 3. 学校のメンタルヘルスの特徴と対策
- 4. 集団および個人で対策を考えるべき事例
- 5. 主に個人で対策を考えるべきこと
- 6. 教育のなかの心の健康の位置づけ
- 7. 子どもを支援する体制
- D. 災害時の精神保健医療活動
- 1. 災害によるストレス
- 2. 急性ストレス反応 : 災害後から1ヵ月位まで
- 3. 心的外傷後ストレス障害 ( PTSD ) : 1ヵ月以上
- 4. 喪失体験による反応 : 災害における死別の特徴
- 5. 生活上のストレスを緩和する : 支援者間の連携と支援の継続
- 6. 救援者のこころのケア : 影の被災者にならないために
- E. 看護職とメンタルヘルス
- 1. 感情を包む容器として機能する看護師
- 2. 共感ストレスと二次的外傷性ストレス
- 3. 看護師の共感疲労とサポートの必要性
- a. 共感疲労とは
- b. 共感疲労の症状
- c. 表層演技と深層演技
- d. 看護師のサポートの必要性
- [3] 精神看護プロセスと援助的人間関係
- A. 個別看護のプロセス
- 1. 感情を通して他者を理解する
- 2. 患者のストーリーを理解する
- 3. 看護過程における問題解決と相互作用
- a. 問題解決方法としてのプロセス
- b. 対人的な相互作用のプロセス
- 4. 援助的人間関係とプロセスレコード
- a. ペプロウのプロセスレコード
- b. オーランドの自己一致
- c. ウィーデンバックの再構成
- d. プロセスレコードの実際
- B. 看護ケアとグループ
- 1. グループの雰囲気
- 2. グループ内の役割と現象
- 3. グループダイナミクス
- 4. 看護師が参加するグループ
- 5. 看護師グループの特徴
- 6. グループの力
- [4] 病院における精神看護
- A. 病院における精神看護
- 1. 入院ケアとタイダルモデル
- a. タイダルモデルとは
- b. タイダルモデル10のコミットメント
- c. タイダルモデルの4つのポイント
- d. 日本におけるタイダルモデルの状況
- 2. 回復段階の看護
- a. 急性期の看護
- b. 慢性期 ( 回復期 ) の看護
- 3. 精神科病棟と看護管理
- a. 安全管理 ( セーフティマネジメント )
- b. 患者の権利擁護 ( アドボカシー )
- B. 児童思春期精神科看護
- a. 子どもへの個別の関わり
- b. 暴力・暴言への対応
- c. 子どもを知る
- d. 外泊・就学への支援
- e. 家族への支援
- f. 集団への関わり
- g. 医療チームの一員としての関わり
- C. リエゾン精神看護
- 1. 患者とその家族へのケア
- 2. 患者・家族を取り巻く医療チームがよりよいケアを提供できるように支援していく
- 3. メンタルヘルス支援
- D. チーム医療と看護
- 1. チーム医療とは
- 2. 精神科におけるチーム医療の必要性
- a. それぞれの専門性を発揮できるチームを目指す
- b. 地域の精神保健福祉を含めたチームを目指す
- 3. チームづくりに大切なこと
- 4. 精神科看護師にとってのチーム医療の有用性
- [5] 症状と精神看護
- A. 睡眠障害
- B. 不安状態
- C. ひきこもり状態
- D. 拒否 ( 拒食, 拒薬 )
- E. 攻撃的行動
- F. 強迫行動
- G. 操作・試し行動
- H. 自傷・自殺企図
- I. 幻覚・妄想
- J. 抑うつ状態
- K. 躁状態
- L. 昏迷状態
- M. 衝動行動
- N. せん妄, もうろう状態, アメンチア
- O. 離脱状態 ( 退薬症候群 )
- P. 認知症
- Q. 発達障害
- [6] 身体合併症の看護
- 1. 麻痺性イレウス
- 2. 嚥下性肺炎
- 3. 糖尿病
- 4. 肺動脈血栓塞栓症
- 5. 多飲症, 水中毒
- 6. 精神科における身体合併症のケア
- [7] 性 ( セクシュアリティ ) をめぐる問題と看護
- 1. セクシュアリティの6要素
- 2. 性をめぐる健康問題について
- a. 制度と治療
- b. DSM - 5 ( アメリカ精神医学会診断 ) による疾患分類
- c. 性別違和とは
- d. セクシュアリティに関連した生きにくさ
- 3. 看護師としての自己認識
- [8] 身体療法と看護
- A. 薬物療法を受ける患者の看護
- 1. 精神科における薬物療法の概観
- a. ストレス - 脆弱性 - 保護因子モデル
- b. 精神科における薬物療法の位置づけ・治療効果
- c. 精神科における治療法の比較
- 2. 薬物療法とアドヒアランス
- a. アドヒアランスが重要な精神科
- b. アドヒアランスに影響する要因
- 3. 精神科における薬物療法の看護の特徴
- a. 心理教育
- b. 精神科における与薬
- c. 服薬自己管理
- B. 電気けいれん療法を受ける患者の看護
- 1. インフォームド・コンセントのサポート
- 2. 実施時および実施後の看護援助
- 3. 患者, 家族の意思決定への援助
- [9] 地域生活における精神看護
- A. 「入院医療中心から地域生活中心」に向けた動き
- 1. 長期入院による弊害
- 2. 地域生活への移行に向けての考え方の転換
- 3. リカバリーとは
- B. リカバリーを支える力 - レジリエンス
- C. 病院 - 地域連携
- 1. 病院 - 地域連携が求められている理由
- 2. 精神科デイケアとは
- 3. デイケアにおける看護師の役割と多職種連携
- 4. 事例 : Mさんの入退院とその後の生活
- 5. 多職種連携に求められるもの
- D. 精神障害者を支える家族
- 1. 精神障害者と家族
- 2. 家族の当事者性
- 3. 家族支援の目的
- 4. アセスメントの視点
- 5. 支援者としての関わり方
- a. 支援関係の構築
- b. 家族全体の自律を支える支援と危機を想定した支援
- [10] 精神看護専門看護師と精神医療
- 1. 精神看護専門看護師の歴史
- 2. 精神看護専門看護師の役割と実践
- a. 専門看護師の6つの役割
- b. 精神看護専門看護師の役割
- c. 精神看護専門看護師の活動と実践
- d. 精神看護専門看護師の活動によってもたらされる効果
- 3. 今後の高度看護実践と医療
- a. 実践能力の向上
- b. 活動の可視化
- c. 役割拡大
- [5. 法と精神医療]
- [1] 精神保健医療と法制度
- A. 精神保健ケアに関する国際的な原則
- 1. 精神疾患を有する者の保護およびメンタルヘルスケアの改善のための原則 ( いわゆる国連原則 )
- 2. 精神保健ケアに関する法 : 基本10原則
- 3. 精神保健に関する法制度の世界的状況と日本の法制度
- B. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
- 1. 法律の沿革
- 2. 精神保健福祉法の基本理念としての人権の尊重
- 3. 精神保健指定医
- 4. 精神科入院形態
- a. 任意入院
- b. 医療保護入院
- c. 応急入院
- d. 措置入院
- e. 移送制度
- 5. 入院中の行動制限, 隔離, 身体的拘束について
- 6. 精神障害者の人権擁護のための制度など
- a. 保護者制度の廃止と今後に向けた取り組み
- b. 精神医療審査会
- c. 実地指導と実施審査
- 7. 精神障害者保健福祉手帳
- 8. 精神保健福祉法改正案についての追加事項
- C. 障害者総合支援法 ( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 )
- 1. 法律の沿革
- 2. 障害者総合支援法の概要
- 3. サービスの種類と利用手続き
- 4. その他障害者に関連する法規
- a. 障害者基本法
- b. 障害者雇用促進法 ( 障害者の雇用の促進等に関する法律 )
- c. 発達障害者支援法
- d. 障害者虐待防止法 ( 障害者虐待の防止, 障害者の養護者に対する支援等に関する法律 )
- e. 障害者差別解消法 ( 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 )
- D. 医療観察法 ( 心神喪失の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 )
- 1. 法律の沿革
- 2. 医療観察法の概要
- 3. 医療観察法による医療の実績
- E. その他の関連法規
- 1. 自殺対策基本法
- 2. 犯罪被害者等基本法
- 3. 児童虐待の防止等に関する法律
- 4. 高齢者虐待の防止, 高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
- 5. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 ( DV法 )
- 6. 健康増進法
- 索引
- 奥付
参考文献
5版の序
P.186 掲載の参考文献
-
1) Marcantonio ER. Delirium in hospitalized older adults. N Engl J Med. 2017;377:1456-66.
-
2) 八田耕太郎, 高橋丈夫, 山城尚人, 他. 救命救急センターの自殺企図患者における抑うつ状態の鑑別. 精神科治療学. 1998;13:191-5.
-
3) 八田耕太郎. せん妄. Clin Neurosci. 2014;32:935-7.
-
4) Litaker D, Locala J, Franco K, et al. Preoperative risk factors for postoperative delirium. Gen Hosp Psychiatry. 2001;23:84-9.
-
5) Davis DH, Muniz Terrera G, Keage H, et al. Delirium is a strong risk factor for dementia in the oldest-old:a population-based cohort study. Brain. 2012;135:2809-16.
-
6) Young J, Murthy L, Westby M, et al. Diagnosis, prevention, and management of delirium:summary of NICE guidance. BMJ. 2010;341:c3704.
-
8) Hatta K, Kishi Y, Wada K, et al. Preventive effects of suvorexant on delirium:a randomized placebo-controlled trial. J Clin Psychiatry. 2017;78:e970-9.
-
9) Asukai N. Suicide and mental disorders. Psychiatry Clin Neurosci. 1995;49(suppl):S91-7.
-
10) 日本臨床救急医学会. 救急医療における精神症状評価と初期対応(PEEC)ガイドブック改訂第2版-多職種で切れ目ない標準的ケアを目指して-. 東京:へるす出版;(印刷中).
-
11) 医療研修推進財団. 精神腫瘍学クイックリファレンス. 東京:創造出版;2009.
-
12) Bush SH, Bruera E. The assessment and management of delirium in cancer patients. Oncologist. 2009;14:1039-49.
-
13) 八田耕太郎, 飛鳥井望. 外傷後精神症状にどう対応するか. 救急医学. 1998;22:982-4.
-
14) Hackett ML, Yapa C, Parag V, et al. Frequency of depression after stroke:a systematic review of observational studies. Stroke. 2005;36:1330-40.
-
15) Suzuki T, Shiga T, Kuwahara K, et al. Depression and outcomes in hospitalized Japanese patients with cardiovascular disease. -Prospective single-center observational study-. Circ J. 2011;75:2465-73.
-
16) Meijer A, Conradi HJ, Bos EH, et al. Prognostic association of depression following myocardial infarction with mortality and cardiovascular events:a meta-analysis of 25 years of research. Gen Hosp Psychiatry. 2011;33:203-16.
-
17) Anderson RJ, Freedland KE, Clouse RE, et al. The prevalence of comorbid depression in adults with diabetes:a meta-analysis. Diabetes Care. 2001;24:1069-78.
-
18) Prince M, Patel V, Saxena S, et al. No health without mental health. Lancet. 2007;370:859-77.
-
19) 八田耕太郎. 精神科救急の現場で何を学ぶか. 精神科救急. 2014;17:113-5.
初版の序
P.213 掲載の参考文献
-
1) The American Group Psychotherapy Association:Clinical Practice Guidelines for Group Psychotherapy. New York:American Group Psychotherapy Association. 日本集団精神療法学会, 監訳. AGPA集団精神療法ガイドライン. 大阪:創元社;2014. p.36-41.
P.215 掲載の参考文献
-
1) 関 則雄, 編. 新しい芸術療法の流れ クリエイティブ・アーツセラピー. 東京:フィルムアート社;2008年.
P.238 掲載の参考文献
-
1) 砂原茂一. リハビリテーション. 東京:岩波新書;1980. p.60.
P.242 掲載の参考文献
-
1) David H. Clark. 秋元波留夫, 北垣日出子, 訳. 精神医学と社会療法. 東京:医学書院;1982.
-
2) 鎌倉矩子, 山根 寛, 二木淑子. 作業療法の世界:作業療法を知りたい・考えたい人のために. 2版. 東京:三輪書店;2004.
-
3) 山根 寛. 精神障害と作業療法. 新版. 東京:三輪書店;2017.
-
4) Mary Law, 他. 吉川ひろみ, 訳. COPM カナダ作業遂行測定. 原著第4版. 東京:大学教育出版;2007.
-
5) Maxwell Jones. 鈴木純一, 訳. 治療共同体を超えて:社会精神医学の臨床. 東京:岩崎学術出版社;1976.
-
6) 鈴木純一. 治療共同体序説. 季刊精神療法. 1984;10:235-42.
-
7) 武井麻子. 精神科看護学ノート. 2版. 東京:医学書院;2005.
-
8) 武井麻子. 感情と看護:人とのかかわりを職業とすることの意味. 東京:医学書院;2001.
-
9) 佐藤幸江. 精神科病院における「接遇」を考える. 精神科臨床サービス. 2010;10:172-7.
P.247 掲載の参考文献
-
1) 野村直樹. やさしいベイトソン コミュニケーション理論を学ぼう. 東京:金剛出版;2008. p.128
-
2) フィリップ・バーカー著. 中村伸一, 信国恵子, 監訳. 家族療法の基礎. 東京:金剛出版;1986/1993. p.68
-
3) レフJ, ヴォーンC 著. 三野善央, 牛島定信, 訳. 分裂病と家族の感情表出. 東京:金剛出版;1985/1991. p.129
P.251 掲載の参考文献
-
1) 厚生労働省ホームページ. 平成28年社会福祉施設等庁舎の概況. http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/16/dl/gaikyo.pdf
P.254 掲載の参考文献
-
1) 高木俊介. 精神障がい者の地域包括ケアにむけて. In:福山愛子, 他編. 精神障害者地域包括ケアのすすめ ACT-Kの挑戦, 〈実践編〉. 東京:批評社;2013. p.9-33.
-
2) 伊藤順一郎, 久永文恵. 第1章ACTの仕組み, 第3章ACT支援の進め方. In:伊藤順一郎, 他監修. ACTブックレット1 ACTのい・ろ・は. 千葉:特定非営利法人地域精神保健福祉機構;2013. p.5-13, p.27-46.
-
3) 厚生労働省. 精神医療保健福祉の改革ビジョンについて, 2004. 厚生労働省ホームページ. http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/09/tp0902-1.html
-
4) 厚生労働省. 精神医療保健福祉の更なる改革に向けて, 2009. 厚生労働省ホームページ. http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/09/s0924-2.html
-
5) ヤーコ・セイックラ, トム・エーリク・アーンキル. 第3章 オープンダイアローグによる危機介入. In:高木俊介, 他訳. オープンダイアローグ. 東京:日本批評社;2016. p.56-70.
-
6) 斎藤 環. 第1部オープンダイアローグとは何か. In:オープンダイアローグとは何か. 東京:医学書院;2015. p.9-78.
-
7) 下平美智代. さらに見えてきたオープンダイアローグ. 精神医療. 2015;18:107-22.
P.267 掲載の参考文献
-
1) 高橋祥友. 医療者が知っておきたい自殺のリスクマネジメント. 2版. 東京:医学書院;2006.
-
2) 高橋祥友. 自殺の危険;臨床的評価と危機介入. 3版. 東京:金剛出版;2014.
-
3) 大原健士郎. 臨床場面における自殺. 臨床精神医学. 1979;8:1255-9.
-
4) World Health Organization:Suicide Rates(per 100,000), by country, year, and gender. http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suiciderates/en/, 2004.
-
5) カール・メニンガー. おのれに背くもの. 東京:日本教文社;1963(Menninger K. Man again Menninger st himself. New York:Harcourt Brace Jovanovich;1938)
-
6) Eisenberg L. Adolescent suicide:On taking arms against a sea of troubles. Pediatrics. 1980;65:315-20.
-
7) 上野正彦, 庄司宗介, 浅川昌洋, 他. 老人の自殺. 日大医誌. 1981;40:1109-19.
-
8) 高橋祥友. 群発自殺. 中公新書. 東京:中央公論新社;1998.
目次
P.279 掲載の参考文献
-
1) Aguilera DC. 著. 小松源助, 荒川義子, 訳. 危機介入の理論と実際. 東京:川島書店;1997.
-
2) バーバラM. ニューマン, フィリップR. ニューマン. 新版生涯発達心理学 エリクソンによる人間の一生とその可能性. 東京:川島書店;1988.
-
3) E. H. エリクソン, 著, 小此木啓吾, 訳. 自我同一性-アイデンティティとライフ・サイクル-. 東京:誠信書房;1959/1973.
-
4) E. H. エリクソン, 他著, 村瀬孝雄, 近藤邦夫, 訳. ライフサイクル, その完結. 増補版. 東京:みすず書房;1998/2001.
-
5) Selye H. A syndrome produced by diverse nocuous agent. Nature. 1936;138:32.
-
6) 鑪幹八郎. アイデンティティとライフサイクル論. 京都:ナカニシヤ出版;2002.
-
7) Wolin SJ, Wolin S, 著, 奥野 光, 小森康永, 訳. サバイバーと心の回復力. 東京:金剛出版;1993/2002. p.12-33.
-
8) フリードマンLJ. エリクソンの人生 アイデンティティの探求者. 上・下. 東京:新曜社;2003.
-
9) Lazarus RS, Folkman S. Stress, appraisal, and coping. New York:Springer;1984.
-
10) 村瀬孝雄, 福島 章, 編著. 臨床心理学大系16臨床心理学の先駆者達. 東京:金子書房;1990.
P.282 掲載の参考文献
-
1) Saunders C. The Management of Terminal Malignant Disease. 2nd ed. London:Edward Arnold;1984. p.232-41.
-
2) E. キューブラー・ロス著, 川口正吉, 訳, 死ぬ瞬間-死とその過程について. 東京:読売新聞社;1998.
-
3) 日本看護協会. 2025年に向けた看護の挑戦. いのち・暮らし・尊厳をまもり支える看護. 2015. p.17.
-
4) 阿部泰之. 第9章アドバンス・ケア・プランニングとベストインタレスト編. In:木澤義之, 他編. いのちの終わりにどうかかわるか. 東京:医学書院;2017. p.274-83.
P.285 掲載の参考文献
-
1) 文部科学省ホームページより引用. http://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/about/004/a004_06.htm
-
2) 文部科学省ホームページより引用. http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1337278.htm
-
3) 児玉隆直, 日本学校メンタルヘルス学会. 「学校メンタルヘルスハンドブック」こころの不調-児童生徒の早期兆候. 東京:大修館書店;2017. p.104-10.
-
4) 文部科学省ホームページより引用. http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1297484.htm
-
5) 文部科学省ホームページより引用. http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/shidou/yougo/1267642.htm
-
6) Kessler RC, Berglund P, Demler O, et al. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication, Arch Gen Psychiatry. 2005;62:593-602.
-
7) McGorry PD. The concept of recovery and secondary prevention in psychotic disorders. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. 1992;26:3-17.
-
8) 篁 宗一. 第5章大学生のメンタルヘルスの危機-仲間づくりの失敗, 2心の病の実態と早期介入の意義. 高校生・大学生のメンタルヘルス対策 学校と家庭でできること. 東京:青弓社;2013.
P.289 掲載の参考文献
-
1) 前田 潤. 被災者と救援者に対する「こころのケア」. In:小原真理子, 他編. 災害看護-心得ておきたい基本的な知識-. 第2版. 東京:南山堂;2012. p.201-22.
-
2) 内閣府. 被災者のこころのケア 都道府県対応ガイドライン. 2012年3月. www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/kokoro.pdf
-
3) 日本集団災害医学会DMATテキスト編集委員会. DMATが知っておくべき災害時の知識『災害超急性期における被災者のこころの変化』. 日本集団災害医学会. DMAT標準テキスト. 東京:へるす出版;2011. p.268-71.
-
4) Underwood P 著/ウイリアムソン彰子, 訳. サバイバー・ギルト:災害後の人々の心を理解するために. 日本災害看護学会誌. 2005;7(2):23-30.
-
5) 槙島敏治, 前田 潤. 災害時のこころのケア. 東京:日本赤十字社;2004. p.26-35.
-
6) 松井 豊. 組織で行うこころのケア『被災職員へのこころのケア』. In:奥寺 敬, 他編. 災害時のヘルスプロモーション2 災害時に向けた施設内教育研修・訓練プログラム. 東京:荘道社;2010. p.281-95.
-
7) 村上典子. 災害時の遺族への対応『グリーフケア』. In:奥寺 敬, 他編. 災害時のヘルスプロモーション2 災害時に向けた施設内教育研修・訓練プログラム. 東京:荘道社;2010. p.259-67.
-
8) 日本集団災害医学会DMATテキスト編集委員会. DMATが知っておくべき災害時の知識『救援者ストレス』. 日本集団災害医学会. DMAT標準テキスト. 東京:へるす出版;2011. p.263-67.
-
9) 兵庫県看護協会災害看護特別委員会. 災害支援ナース実践マニュアル. 兵庫:兵庫県看護協会. 2012年1月.
-
アメリカ国立子どもトラウマティックストレス・ネットワークアメリカ国立PTSDセンター. サイコロジカル・ファーストエイド実施の手引き第2版. 兵庫県こころのケアセンター訳, 2009年3月. http://www.j-hits.org/
P.291 掲載の参考文献
-
1) Figley CR. 共感疲労-ケアの代償についての新しい理解に向けて-. In:BH. スタム, 編. 小西聖子, 金田ユリ子, 訳. 二次的外傷性ストレス 臨床家, 研究者, 教育者のためのセルフケアの問題. 東京:誠信書房;1999/2003. p.4
P.297 掲載の参考文献
-
1) Sullivan HS, 著. 中井久夫, 山口 隆, 訳. 現代精神医学の概念. 東京:みすず書房;1940/1976. p.3.
-
2) Henderson V. ザ・ナーシング・プロセス-この呼び名はこれでよいのだろうか? In:Halloran EJ. 小玉香津子, 訳. ヴァージニア・ヘンダーソン選集-看護に優れるとは-. 東京:医学書院;1995/2007. p.163
-
3) Peplau HE, 著. 稲田八重子, 小林富美栄, 武山満智子, 他訳(1973)人間関係の看護論. 東京:医学書院;1952/1973. p.5, p.325
-
4) 宮本真巳. ペプロウの援助関係からナラティブ・アプローチへ. 精神科看護. 2015;42:28-37.
-
5) Orlando IJ, 著. 池田明子, 野田道子, 訳. 看護過程の教育訓練. 東京:現代社;1972/1977. p.32
-
6) Wiedenbach E, 著. 外口玉子, 池田明子, 訳, 臨床看護の本質-患者援助の技術-. 東京:現代社;1964/1969. p.108.
P.301 掲載の参考文献
-
1) 武井麻子. グループと精神科看護. 東京:金剛出版;2012. p.132-3.
P.303 掲載の参考文献
-
1) 秋山 剛. タイダルモデル導入の経緯と, 治療における位置づけ. 特集2 タイダルモデルで行う院内自殺予防. 看護管理. 2013;23:482-4.
-
2) Brookes N. Unit V Middle Range Nursing Theories, 32. Phil Barker:The Tidal Model of Mental Health Recovery. In:Alligood MR, editor. Nursing Theorists and their work. 8 ed. St. Louis Missouri:elsever mosby;2014. p.626-56.
-
3) フィル・バーカー, ポピー・ブキャナン・バーカー. 英国にみる精神看護実践モデルーメンタルヘルスの回復についてのタイダルモデル. 萱間真美 野田文彦, 編. 看護学テキストNICE 精神看護学 こころ・からだ・かかわりのプラクティス. 東京:南江堂;2010.
-
4) 尾形潤子, 秋山美紀. 管理者の視点から見たタイダルモデル. 特集2 タイダルモデルで行う院内自殺予防. 看護管理. 2013;23:495-6.
P.312 掲載の参考文献
-
1) 船越明子, 田中敦子, 服部希恵, 他. 児童・思春期精神科病棟におけるケア内容-看護師へのインタビュー調査から-. 日本看護学会論文集-小児看護-. 2010;41:191-4.
P.317 掲載の参考文献
-
1) 厚生労働省. チーム医療の推進について. http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/03/dl/s0319-9a.pdf
-
2) 厚生労働省. 長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策の方向性. http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000051138.pdf
-
3) 前川早苗. チームビルディング. In:宇佐美しおり. 精神看護スペシャリストに必要な理論と技法. 東京:日本看護協会出版会;2009. p.144-9.
P.333 掲載の参考文献
-
1) 吉浜文洋. 学生のための精神看護学. 東京:講談社;2010. p.226-9.
-
2) 太田保之. 学生のための精神医学. 3版. 東京:医歯薬出版;2015. p.112-7.
-
3) 阿保順子. 境界性人格障害患者の理解と看護. 東京:精神看護出版;2008. p.36-53.
-
4) 坂田三允. 精神科エスクペール20衝動性と精神看護. 東京:中山書店. 2007. p.88-99
-
5) 吉松和哉. 精神看護学I精神保健学. 6版. 東京:ヌーヴェルヒロカワ;2015. p.272-7.
P.351 掲載の参考文献
-
1) ブライトンJC. 敵を知る. In:都甲 宗, 監訳. もの忘れと認知症"ふつうの老化"をおそれるまえに. 東京:みみず書房;2010. p.3-18.
-
2) 六角僚子. 認知症に伴う症状. In:認知症ケアの考え方と技術. 東京:医学書院;2015. p.13-27.
-
3) 萩野悦子. 認知症の長期経過とケア. 老年精神医学雑誌. 2009;20:646-50.
-
4) 加藤伸司. 認知症に対する心理的アプローチの重要性. 老年精神医学雑誌. 2017;28:1335-41.
P.360 掲載の参考文献
-
1) ゲイル・W・スチュアート, ミシェル・T・ラライア, 著. 安保寛明, 宮本有紀, 監訳. 精神科看護-原理と実践. 原著第8版. 東京:エルセビア・ジャパン;2007.
-
2) 井上令一, 監修・カプラン臨床精神医学テキスト DSM-5診断基準の臨床への展開. 日本語版第3版/原著第11版. 東京:メディカル・サイエンス・インターナショナル;2016.
P.365 掲載の参考文献
-
1) 日本神経精神薬理学会. 統合失調症薬物治療ガイドライン. http://www.asas.or.jp/jsnp/img/csrinfo/togoshiccho_01.pdf p23
-
2) 国立精神・神経医療研究センター. うつ病に対する認知行動療法の効果. http://www.ncnp.go.jp/cbt/cbtcenter.pdf
P.369 掲載の参考文献
-
1) Rapp CA, Goscha RJ, 著. 田中英樹, 監訳. ストレングスモデル-リカバリー志向の精神保健福祉サービス-. 3版. 東京:金剛出版;2014. p.130-5.
-
2) Ragins M, 著. 前田ケイ, 監訳. ビレッジから学ぶ リカバリーへの道 精神の病から立ち直ることを支援する. 東京:金剛出版;2005. p.28-30.
-
3) Herman JL, 著. 中井久夫, 訳. 心的外傷と回復. 増補版. 東京:みすず書房;1999. p.191.
-
4) 中井久夫, 山口直彦. 看護のための精神医学. 2版. 東京:医学書院;2004. p.218.
-
5) Herman JL, 著. 中井久夫, 訳.心的外傷と回復. 増補版.東京:みすず書房;1999. p.205.
-
6) Wolin SJ, Wolin S, 著. 奥野 光, 小森康永, 訳. サバイバーと心の回復力 逆境を乗り越えるための七つのリジリアンス. 東京:金剛出版;2002. p.13-4.
P.372 掲載の参考文献
-
1) 厚生労働省HP. "地域精神保健医療体制の現状について". www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai.../0000118923.pdf.
-
2) 厚生労働省HP. "地域精神保健医療体制の現状について". www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai.../0000118923.pdf.
-
3) 厚生労働省HP. "地域精神保健医療体制の現状について". www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai.../0000118923.pdf.
-
4) 福田祐典. 多機能垂直統合を精神科医療政策との関わりから考える. In:窪田 彰, 編. 多機能型精神科診療所による地域づくり-チームアプローチによる包括的ケアシステム. 東京:金剛出版;2016. p.59-67.
P.379 掲載の参考文献
-
1) 森山美知子. スペシャリストの行方, インターナショナルナーシングレビュー. 1995;18:4-39.
-
2) アメリカ看護師協会. アメリカ公衆衛生協会公衆衛生看護部, 編. 小玉香津子, 高崎絹子, 訳. いま改めて看護とは. 東京:日本看護協会出版会;1984.
-
3) 加藤令子. 日本におけるスペシャリストの役割拡大の背景. インターナショナルナーシングレビュー. 2003;26:10-3.
-
4) G. W. スチュアート, S. J. サンディーン, 編. 樋口康子, 他監修, 稲岡文昭, 訳. リエゾンナーシング-看護実践のための1モデル, 新臨床看護学体系 精神看護学II. 東京:医学書院;1986. p.643-56.
-
5) 宇佐美しおり. 精神看護専門看護師の現状と課題. In:宇佐美しおり, 編. 精神科看護の理論と実践-卓越した看護実践をめざして-. 東京:ヌーヴェルヒロカワ;2010. p.215-9.
-
6) 野末聖香. 精神看護専門看護師およびリエゾン精神看護学の歴史. In:宇佐美しおり, 編. 精神科看護の理論と実践-卓越した看護実践をめざして-. 東京:ヌーヴェルヒロカワ;2010. p.10-3.
-
7) 日本学術会議健康・生活科学委員会看護学分科会. 提言 高度実践看護師制度の確立に向けて-グローバルスタンダードからの提言-. 日本学術会議;2011. p.1-21.
-
8) 宇佐美しおり. 精神科における退院支援・地域支援. 日本の精神医療・精神看護の現状と課題, 地域生活移行支援の実態. 地域連携入退院支援. 2012;5:85-9.
-
9) 日本看護科学学会. 第15回公開シンポジウム「わが国における高度看護実践看護師のグランドデザイン. 日本看護系学会協議会, 日本学術会議. 2012.12.1. http://www.jana-office.com/sympo/sympo15_20130304.pdf
-
10) 宇佐美しおり. 精神看護の発展と精神看護専門看護師の役割. 現代のエスプリ;2010;1:115-22.
-
11) 宇佐美しおり. CNSが考える看護職の役割拡大. インターナショナルナーシングレビュー. 2009;32:21-3.
-
12) 平成30年度版. 高度実践看護師教育課程基準. 高度実践看護師教育課程審査要項. 日本看護系大学協議会:2018. http://www.janpu.or.jp/download/pdf/cns.pdf
-
13) 日本看護協会. 専門看護師とは. http://nintei.nurse.or.jp/nursing/qualification/cns
-
14) 宇佐美しおり. 精神看護専門看護師の役割と活動. 病院・地域精神医学. 2010;52:23-5.
-
15) 日本専門看護師協議会:精神看護専門看護師の活動. http://www.jpncns.jp/ch5/poster/2012_08_01/seisinn_08_poster.pdf
-
16) 田中美恵子. 高度実践看護師の役割拡大のために修士課程のあり方について. 実践を変革する高度実践看護師の発展をめざして. 学術の動向. 2014;9:66-71.
-
17) 宇佐美しおり. 精神看護専門看護師および専門看護師育成者の立場から. 高度実践看護師を核とした新たな医療提供システムへの提言. APN看護卒後教育におけるMid-level provider育成と医療提供イノベーション事業機関誌. 2014;3:4-6.