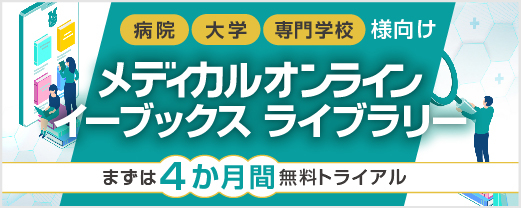| 書籍名 |
脳血管障害の評価とアプローチ |
| 出版社 |
文光堂
|
| 発行日 |
2014-06-16 |
| 著者 |
|
| ISBN |
9784830645105 |
| ページ数 |
241 |
| 版刷巻号 |
第1版第2刷 |
| 分野 |
|
| シリーズ |
生活の行為を紡ぐ作業療法プラクティス
|
| 閲覧制限 |
未契約 |
臨床の現場で,「何を観察し,どのような情報を入手し,何を考え,何をしているか」というクリニカルリーズニング(臨床推論)を,図表などで表現している.住み慣れた地域での暮らしを積極的に支援する作業療法士の役割を踏まえ,急性期から生活維持期までシームレスに作業療法を提供するために役立ち,臨床実践の思考過程の一助となるだけではなく,あらためて回復期での作業療法を考え直すことができる,多くの作業療法士の参考となる一冊.
目次
- 表紙
- 常任編集 / 執筆
- 序
- 目次
- PART I 生活を見据えた作業療法の取り組み
- 1. 急性期
- 脳血管障害リハビリテーションの流れを理解しよう !
- 急性期から作業療法士が関わる意義とはなんだろう ?
- 急性期の状態像を把握しておこう !
- 作業療法実践ステップI~基本情報を収集し, リスク管理を行うことが第一歩 ! ~
- 作業療法実践ステップII~作業療法を始める前にあたっての確認事項 ! ~
- 作業療法実践ステップIII~急性期における基本プログラム~
- 急性期から生活を見据えた作業療法を展開していこう ! ~
- 急性期は, 家族との関わりの重要な時期である !
- 回復期への移行にあたって申し送りをしっかりと !
- 2. 回復期 ( 回復期リハビリテーション病棟 )
- 回復期リハビリテーション病棟とは
- 回復期リハビリテーション病棟におけるリハビリテーションの流れ
- モーニング・イブニング訓練 ( ケア ) で押さえておくべき視点
- OTが病棟生活のなかに入り込んで何をみるか ( ADL, その人の生活ぶり, 自発性, 他者とのコミュニケーション, 障害を負ってもいきいきと生活しているか ?)
- 他職種とのコミュニケーションをどのように活かすか ?
- 家族との関係で見えてくる退院後の生活
- 3. 移行期
- 回復期と維持期の境目に位置する移行期を考えるには, 回復期と維持期の両面から考える必要がある
- 移行期リハビリテーションを実施する
- 介護老人保健施設を例に「作業療法士の役割」を考える
- 4. 在宅生活期 ( 地域 )
- 維持期における作業療法士の役割
- 維持期の流れと作業療法の特徴
- PART II 評価技術
- 1. 情報収集と評価の組み立て方
- 評価にあたっての心得
- 評価の流れ
- ミニレクチャー 指示書や診療録でわかること
- ミニレクチャー コミュニケーションがとりにくい患者からの情報の聞き出し方
- 2. 観察と全体像への結びつけ方
- なぜ観察するのか
- 何をみるか
- 全体をみるとはどういうことか
- ミニレクチャー 何を見るか(1) 表情や言動
- ミニレクチャー 何を見るか(2) 姿勢や行動
- ミニレクチャー 何を見るか(3) 自宅での生活場面で
- ミニレクチャー 何を見るか(4) 地域や社会の生活場面で
- 3. 患者一人ひとりの生活をみるADL評価
- 生活をみるためには患者の声をよく聴くこと
- 「できるADL」と「しているADL」の評価について
- 患者にとってADLとは
- ミニレクチャー 夜間のトイレ動作の評価とアプローチ
- 4. 意味のある作業を見つけるために
- 意味のある作業とは ?
- 回復期の特徴
- 評価の場面で
- 毎日の訓練のなかから
- 「意味のある作業」が見つかるとき
- 手がかりになる評価法
- 5. 再発や転倒の危険と作業療法での評価
- 再発
- 転倒
- ミニレクチャー 表面化しない症状に気づくとき~車椅子上で右に傾くAさん~
- 6. 目標の設定方法
- 良い目標の設定とは ?
- 情報を提供する
- 目標を共有する
- ミニレクチャー 回復期病棟から「どこに」退院するのかを決めるとき
- PART III 治療技術
- 1. 生活で使える上肢を目指して
- 患者の訴えを「よく聴くこと・よく観ること」が最良の評価である !
- 「上肢機能」ではなく, それぞれの「上肢の機能」を思い起こそう !
- 「上肢の機能」と「生活行為のなかの動き ( 機能 ) 」の相互関係に着目しよう !
- 「作業療法の基本方針」立案は,「生活行為のなかの動き ( 機能 ) 」の相互関係から
- 「作業療法アプローチ」の立案 ?「ペグを移動すること」が目的ではない ?
- 2. 上肢をうまく使えるようにするために
- 上肢機能回復の理論を知ろう
- 「うまく使う」ようにするために必要な評価とは何だろう
- 効果的に訓練を進めるコツ
- ミニレクチャー フィードバック制御とフィードフォワード制御の機能
- ミニレクチャー 肩の痛み ( 予防と対処 )
- 3. 上肢をうまく使うための訓練のバリエーション ( 進め方, やり方 )
- 麻痺手の状態を理解しよう !
- 訓練の進め方の基本をマスターする
- 上肢の機能回復を図る代表的なアプローチとは ?
- 麻痺手の状態に応じたアプローチ方法
- ADL・IADL訓練を忘れるべからず !!
- 4. 体幹と下肢の機能と作業療法
- 体幹と下肢の役割を知ろう !
- 姿勢と動きの特徴を知ろう !
- 客観的評価
- 臨床評価
- 体幹と下肢への作業療法アプローチ
- ミニレクチャー 姿勢調節をうまく機能させる
- ミニレクチャー 上肢帯の動きと上肢・体幹の機能
- ミニレクチャー 患者の在宅生活をイメージした移動の考え方
- 5. 高次脳機能障害と生活との関連の捉え方
- 生活場面での困り事の背景を明らかにする
- 急性期~回復期のベッド上での活動に限定される時期は, 認知機能の廃用を予防する
- 回復期 : 道具の扱い方や作業手順の進め方に注目し, 動作を分解して誤り ( エラー ) の特徴をみて症状を鑑別する
- 失語症がテストや活動場面に及ぼす影響を考慮する
- 生活行為を再編する : できることを増やし, 誤りが生じないように環境を変える
- 実生活に即して練習する
- 回復期から地域生活移行期 : 医学的リハビリテーションから地域社会への切れ目ない ( シームレス ) 移行を図る
- 支援の輪を広げる
- ミニレクチャー 失語症を有する患者とのコミュニケーション
- ミニレクチャー 重度の失行症患者への関わり方
- ミニレクチャー テストバッテリーでは表面化しない機能
- 6. こころのケア
- 脳血管障害患者の多くは戸惑いや先行きの見えない不安を抱えていることを知る !!
- 高次脳機能障害の有無でアプローチは異なる !!
- 脳血管障害患者が不安を解消し生活を再構築するための3つのポイントを押さえる !!
- 拒否されるときは…
- 作業療法を展開するときの大前提は…
- ミニレクチャー 回復に大きな期待を抱いている患者には ?
- 7. 1)「できるADL, IADL」をいかに「しているADL, IADL」にするか
- 評価に基づいて具体的な生活目標を設定する
- 「できる活動」を訓練にて獲得する
- 「している活動」として定着させ, 生活の習慣にする
- 症例紹介
- まとめ
- ミニレクチャー なかなか「自分でしようとしない」患者への対応は ?
- ミニレクチャー どこまでアプローチしてよいのか ?
- 7. 2) 365日リハビリテーション実施体制と作業療法の提供の仕方・考え方
- なぜ, 365日リハビリテーション実施体制が求められたのか ?
- リハビリテーション医療における作業療法の機能・役割は何か ?
- 365日リハビリテーションの実施の現状はどうか ?
- 365日リハビリテーションサービスを提供するにはどのような工夫が必要か ?
- ミニレクチャー 退院前訪問指導の実際
- 8. 多職種間の連携と目標設定の考え方
- 多職種間連携における3つのチームモデル
- モーニングケア ( 早出 ) やイブニングケア ( 遅出 ) をどう捉えるか
- 目標設定の考え方
- ミニレクチャー 作業療法の評価結果をどのように多職種に伝えるか
- 9. 退院先への情報の提供
- 有用な情報とは何か ?
- 症例を通して具体的にイメージしてみよう !
- ミニレクチャー 急性期施設から回復期施設への情報は
- ミニレクチャー 回復期施設から移行期施設への情報は
- ミニレクチャー 回復期施設から在宅・地域施設への情報は
- ミニレクチャー 施設外の作業療法士に伝えることと他職種に伝えること
- 索引
- 奥付
参考文献
PART I 生活を見据えた作業療法の取り組み
P.10 掲載の参考文献
-
1) 豊田彰宏:脳卒中急性期リハビリテーションとリスク管理. OTジャーナル 39(3):190-194, 2005
-
2) 日本作業療法士協会学術部 編:脳卒中急性期作業療法の実際1-リスク管理, 評価. 作業療法マニュアル 43 脳卒中急性期の作業療法, pp9-16, 2011, 日本作業療法士協会
-
3) 森山早苗:脳血管障害. 作業療法学全書[改訂第3版]第4巻 作業治療学1 身体障害(日本作業療法士協会監修), pp58-60, 2008, 協同医書出版社
-
4) 花岡寿満子, 清水万紀子:脳血管障害. 図解作業療法技術ガイド(石川 齊, 古川 宏 編), pp316-331, 2000, 文光堂
-
5) 田崎義昭, 斎藤佳雄:ベッドサイドの神経の診かた[改訂17版], pp283-284, 2010, 南山堂
-
6) 井上 剛, 木村和美, 山口武典:脳血管障害急性期の内科的治療とリスク管理. 理学療法MOOK 1 脳損傷の理学療法1 超早期から急性期のリハビリテーション[第2版](吉尾雅春 編), pp8-18, 2009, 三輪書店
-
7) 横田一彦:急性期の事故防止. 理学療法MOOK 1 脳損傷の理学療法1 超早期から急性期のリハビリテーション[第2版](吉尾雅春 編), pp104-111, 2009, 三輪書店
-
8) 澤本広美, 新田真代, 下村美穂, 他:急性期から考える「その人らしさ」. OTジャーナル 39(3):224-228, 2005
P.17 掲載の参考文献
-
1) 年度毎 病床届出数及び累計数. 回復期リハビリテーション病棟の都道府県別データ(平成25年12月27日資料)[internet] http://www.rehabili.jp/source/0110/1.pdf, 回復期リハビリテーション病棟協会
-
2) 石川 誠氏(初台リハビリ病院理事長・長嶋茂雄監督主治医)の講演より. より良きケアのために, 2006-03-01[internet] http://blog.goo.ne.jp/hunet01/e/c0be56426d1fb75dde0848d6cc03fe07, ヒューネット介護情報室
-
3) 医科診療報酬点数表. 中央社会保険医療協議会 総会(第272回)議事次第[internet] http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000037011.pdf 2014, 厚生労働省
-
4) 山中誠一郎:回復期リハビリテーション病棟におけるセラピストの役割-初台リハビリテーション病院の試み-. リハビリテーションひろば 50:10-22, 2012
-
5) 関谷 修:回復期リハビリテーション病棟におけるセラピストの役割-東京都リハビリテーション病院の試み-. リハビリテーションひろば 50:23-30, 2012
-
6) 友利幸之介, 東登志夫, 室谷直美, 他:更衣動作を中心とした病棟ADL訓練によって生活全般が活性化した一症例-回復期リハビリテーション病棟での経験を通して-. 長崎大学医学部保健学科紀要 16(1):57-61, 2003
-
7) 谷川正浩:病棟での協働. 覗いてみたい!? 先輩OTの頭の中, pp125-133, 2006, 三輪書店
P.21 掲載の参考文献
-
1) 厚生省保険局:第1章 基本診療料. 社会保険・老人保健診療報酬 医科点数表の解釈 平成12年4月版, p92, 2000, 社会保険研究所
-
1) 山田和彦:さまざまなリハビリテーションサービス(4)老人保健施設. 維持期リハビリテーション(日本リハビリテーション病院・施設協会 編), pp26-31, 2009, 三輪書店
-
2) 斉藤秀之:急性期・回復期から生活期リハビリテーションへ. 地域リハ 7(11):894-898, 2012
-
2) 厚生省 平成9年度 維持期におけるリハビリテーションのあり方に関する検討委員会:平成9年度 維持期におけるリハビリテーションのあり方に関する検討委員会報告書, 1997, 日本公衆衛生協会
-
3) 加藤ふみ子:回復期リハビリテーション病棟におけるチーム育成のための戦略-「ADLの充実」に向けて組織での取り組み. 地域リハ 3(10):933-936, 2008
-
4) 谷川正浩:機能障害・ADLの早期改善と自立, そしてIADLに向けて-リハスタッフの課題について. 地域リハ 3(10):937-939, 2008
P.26 掲載の参考文献
-
1) 浜村明徳:維持期リハビリテーションとは. 維持期リハビリテーション(日本リハビリテーション病院・施設協会編), p7, 2009, 三輪書店
-
1) 日本リハビリテーション病院・施設協会 編:介護保険とリハビリテーション, 1999, 三輪書店
-
2) 矢野浩二:通所リハビリテーション. 維持期リハビリテーション(日本リハビリテーション病院・施設協会編), p14, 2009, 三輪書店
-
2) 大田仁史 編:地域リハビリテーション論, 2004, 三輪書店
-
3) 澤村誠志 監修:地域リハビリテーション白書 3, 2013, 三輪書店
-
3) 浜村明徳:地域リハビリテーション充実に向けた課題. 全国地域リハビリテーション支援事業連絡協議会 第3回ブロック大会in湯布院, 講演資料p31, 図29, 2010
-
4) 大田仁史:終末期リハビリテーションの定義. 大田仁史講演集(3)介護予防と終末期リハビリテーション, p92, 2009, 荘道社
-
4) 山本和儀 編著:ノーマライゼーションの町づくり, 1997, 医歯薬出版
-
5) 大田仁史:終末期リハビリテーションの具体的な手法. 大田仁史講演集(3)介護予防と終末期リハビリテーション, p95, 2009, 荘道社
-
5) 茨木美穂, 佐藤義信, 佐藤浩二, 他:リハビリテーションの視点に立った退院援助計画「経過的ケアプラン」の実践. 総合ケア 14(8):50-55, 2004
-
6) 大田仁史:大切な二つの線. 大田仁史講演集(3)介護予防と終末期リハビリテーション, p63, 2009, 荘道社
PART II 評価技術
P.36 掲載の参考文献
-
1) 日本作業療法士協会:平成23年度老人保健健康増進等事業 生活行為向上マネジメントの普及啓発と成果測定研究事業 人は作業をすることで元気になれる, 2012
-
2) 若林秀隆:PT・OT・STのためのリハビリテーション栄養-栄養ケアがリハを変える, 2010, 医歯薬出版
-
3) Gary Kielhofner編著, 山田 孝 監訳:人間作業モデル-理論と応用, 2007, 協同医書出版社
-
4) 吉川ひろみ:COPM・AMPSスターティングガイド, 2008, 医学書院
-
5) 岩瀬義昭, 大庭潤平, 村井千賀, 他編:"作業"の捉え方と評価・支援技術 生活行為自立に向けたマネジメント, 2011, 医歯薬出版
-
6) 作業選択意思決定支援ソフト(ADOC), https://sites.google.com/site/adocforot/kaihatsu-made
P.49 掲載の参考文献
-
1) 長山洋史, 水野勝広, 中村祐子, 他:日常生活上での半側無視評価法Catherine Bergego Scaleの信頼性, 妥当性の検討. 総合リハビリテーション 39:373-380, 2011
-
2) Fisher AG:Assessment of Motor and Process Skills, vol.1:Development, Standardization, and Administration Manual, 5th ed, 2003, Three Star Press, Colorado
-
3) Fisher AG:Assessment of Motor and Process Skills, vol.2:user manual, 5th ed, 2003, Three Star Press, Colorado
-
4) 斉藤さわこ:運動技能とプロセス技能の評価(AMPS). OTジャーナル 38:533-539, 2005
P.56 掲載の参考文献
-
1) 松本琢磨, 瀬戸初恵, 松田哲也, 他:評価面接・作業面接のコツ身体障害-臨床での面接, 動作分析から導き出す, 患者の治療・支援計画-. 作業療法ジャーナル 42(6):518-525, 2008
P.60 掲載の参考文献
-
1) 国立社会保障・人口問題研究所[internet], http://www.ipss.go.jp/, 日本の将来推計人口(平成24年1月推計, 表1-1)
P.68 掲載の参考文献
-
1) 齋藤 宏, 矢谷令子, 丸山仁司:姿勢と動作 第3版 ADLその基礎から応用, 2010, メヂカルフレンド社
-
1) 千野直一:FIMの評価方法. 脳卒中患者の機能評価(千野直一 編著), pp52-85, 1997, シュプリンガー・ジャパン
-
2) 細田多穂:日常生活活動学テキスト(河元岩男, 坂口勇人, 村田 伸 編), pp23-24, 2011, 南江堂
-
3) 谷川正浩:覗いてみたい!? 先輩OTの頭の中, 2006, 三輪書店
-
4) 古川 宏:作業療法のとらえ方, 2005, 文光堂
P.80 掲載の参考文献
-
1) 村井千賀:生活行為向上マネジメントとは. 作業療法ジャーナル 47(5):390-395, 2013
P.87 掲載の参考文献
-
1) 小林祥泰, 他:I. 脳卒中一般 3-1. 脳卒中一般の危険因子の管理. 脳卒中治療ガイドライン2009[internet] http://www.jsts.gr.jp/jss08.html, 篠原幸人, 他 脳卒中合同ガイドライン委員会編, 日本脳卒中学会
-
2) 土肥 豊:片麻痺における心疾患の合併と治療上のリスク. 理療と作療 5(6):441, 1971
-
3) 里宇明元, 他:リハビリテーションの中止基準. リハビリテーション医療における安全管理・推進のためのガイドライン(日本リハビリテーション医学会診療ガイドライン委員会 編), p6, 2006, 医歯薬出版
-
4) 中村隆一, 齋藤 宏, 長崎 浩:7 姿勢. 基礎運動学 第6版, pp336-338, 2003, 医歯薬出版
P.99 掲載の参考文献
-
1) 長谷川幹:主体性をひきだすリハビリテーション 教科書をぬりかえた障害の人々, pp2-42, 322-327, 2009, 日本医事新報社
-
2) 川越雅弘:マネジメントとは-基本的考え方とその進め方を中心に-, 生活行為向上マネジメントの質の評価方法の開発と質の向上のあり方検討事業研究説明会資料, 2013
-
3) 沼野一男:情報化社会と教師の仕事, pp51-66, 1986, 国土社
-
4) 佐藤良枝:『Buon Giorno!』作業療法士Sより...[internet], http://yoshiemon.at.webry.info/
-
5) 井上和章:"ながら力"が歩行を決める 自立歩行能力を見きわめる臨床評価指標「F&S」, pp63-112, 2011, 協同医書出版社
-
6) 井上和章, 清水ミッシェル・アイズマン, 沖田一彦:脳卒中片麻痺者の自立歩行能力判定:バランス評価スケールと歩行時の二重課題を組み合わせて, 理学療法科学 25(3):323-328, 2010
-
7) 杉本 諭, 丸谷康平: 脳卒中片麻痺患者の歩行能力とFunctional Balance Scale下位項目の関係, PTジャーナル 39:547-663, 2005
-
8) 北地 雄, 原 辰成, 佐藤優史, 他: 回復期リハビリテーション病棟に入院中の脳血管疾患後片麻痺を対象とした歩行自立判断のためのパフォーマンステストのカットオフ値, 理学療法学 38:481-488, 2011
-
9) 道免和久 編著:脳卒中機能評価・予後予測マニュアル, pp81-167, 2013, 医学書院
-
10) 二木 立, 上田 敏:脳卒中の早期リハビリテーション, 1992, 医学書院
-
11) Mary Law 編著:クライエント中心の作業療法 カナダ作業療法の展開, pp95-130, 2000, 協同医書出版社
-
12) 吉川ひろみ:作業療法がわかるCOPM・AMPSスターティングガイド, 2008, 医学書院
-
13) ヘルスリテラシー 健康を決める力[internet], http://www.healthliteracy.jp/
-
14) 大越 満:政令市新潟-月1,000件の訪問リハを実践する診療所あり, 地域リハ 2:545-547, 2007
-
15) 大越 満:目標と実施期間を設定した訪問リハビリテーションの実践-3つのコースを設定して-, 全国訪問リハビリテーション研究会第19回全国大会抄録集, 2012
PART III 治療技術
P.110 掲載の参考文献
-
1) 障害者福祉研究会 編:ICF 国際生活機能分類-国際障害分類改訂版-, pp137-145, 2003, 中央法規出版
-
2) 鎌倉矩子:手のかたち 手のうごき, 1989, 医歯薬出版
-
3) 日本作業療法士協会:平成21年度老人保健健康増進等事業「自立支援に向けた包括マネジメントによる総合的なサービスモデル調査研究報告書」
-
4) 日本作業療法士協会学術部 編:作業療法関連用語集 改訂第2版, p65, 2011, 日本作業療法士協会
-
5) 日本作業療法士協会 監修:"作業"の捉え方と評価・支援技術 生活行為の自律に向けたマネジメント, pp28-29, 2011, 医歯薬出版
P.116 掲載の参考文献
-
1) Ward NS, Cohen LG:Mechanism underlying recovery of motor function after stroke. Archives Neurology 61:1844-1848, 2004
-
2) 原 行弘:脳卒中上肢に対する治療. 総合リハ 38:711-717, 2009
-
3) 鎌倉矩子 他:『NOMA・上肢機能診断』公式ホームページ[internet], http://www.noma-handlab.com, NOMAハンド・ラボ
-
4) 野崎大地:運動学習研究の知見に基づいたリハビリテーションストラテジー. クリニカルリハ 16:913-918, 2007
P.120 掲載の参考文献
-
1) 川人光男:脳の計算理論, 1996, 産業図書
-
1) 松村道一, 小田伸午, 石原昭彦 編著:脳百話-動きの仕組みを解き明かす-, 2003, 市村出版
-
2) 川人光男:脳の仕組み, 1992, 読売新聞社
-
3) 道免和久:CI療法 脳卒中リハビリテーションの新たなアプローチ, 2008, 中山書店
P.123 掲載の参考文献
-
1) Lindgren I, et al:Shoulder pain after stroke, Stroke 38:343-348, 2007
P.131 掲載の参考文献
-
1) 松尾 篤:脳卒中片麻痺患者の上肢機能改善のためのアプローチの最近の動向, 理学療法 29:1333-1340, 2012
-
2) 高見彰淑:脳卒中片麻痺患者の手指把持機能改善のためのアプローチ, 理学療法 29:1360-1366, 2012
-
3) 坂本祐子 他:脳卒中患者の治療器具キャスター付手指外転板の上肢機能効果-表面筋電計を用いて-, 作業療法ジャーナル 26:136-140, 1992
P.138 掲載の参考文献
-
1) 日本作業療法士協会 監修:作業治療学1[身体障害], 作業療法学全書[改訂第2版]第4巻, 2004, 協同医書出版社
-
1)吉尾雅春, 松田淳子, 山下顕史, 他:片麻痺の頚・体幹・骨盤帯運動機能検査法の改良, 理学療法学, 22(Supplement 2):296, 1995
-
2) 松田淳子, 野谷美樹子, 檀辻雅広, 他:頚・体幹・骨盤帯運動機能検査の信頼性, 理学療法学, 25(Supplement 2):404, 1998
-
2) 中村隆一, 齋藤 宏:基礎運動学 第5版, pp105-143, 2000, 医歯薬出版
-
3) 江藤文夫, 他:VII. リハビリテーション 2-2. 歩行障害に対するリハビリテーション, 脳卒中治療ガイドライン2009(篠原幸人, 他 脳卒中合同ガイドライン委員会編), p300, 2009, 協和企画
-
3) 日本車いすシーティング協会 編:改訂版車いす・シーティング-その理解と実践-, 2009, はる書房
-
4) Fugl-Meyer AR, Jaasko L, Leyman I, et al:The post-stroke hemiplegic patient. l. a method for evaluation of physical performance. Scand J Rehabil Med 7(1):13-31, 1975
-
5) 丸山仁司 編:考える理学療法 評価から治療手技の選択[中枢神経疾患編], 2010, 文光堂
P.140 掲載の参考文献
-
1) 中村隆一, 齋藤 宏:基礎運動学 第5版, pp105-143, 2000, 医歯薬出版
-
2) 日本車いすシーティング協会 編:改訂版車いす・シーティング-その理解と実践-, 2009, はる書房
P.142 掲載の参考文献
-
1) 中村隆一, 齋藤 宏, 長崎 浩:4 四肢と体幹の運動. 基礎運動学 第6版, pp205-208, 2003, 医歯薬出版
P.152 掲載の参考文献
-
1) 鎌倉矩子, 種村留美, 山崎せつ子:作業療法マニュアル 30 高次神経障害の作業療法評価, 2002, 日本作業療法士協会
-
2) 相澤病院リハビリテーション科:高次脳機能障害ポケットマニュアル 第2版(原 寛美 監修), 2011, 医歯薬出版
-
3) 甲斐雅子, 長谷川敬一, 村山幸照 他:作業療法マニュアル 43 脳卒中急性期の作業療法, pp20-24, 2011, 日本作業療法士協会
-
4) 橋本圭司:高次脳機能障害 診断・治療・支援のコツ, pp60-62, 2011, 診断と治療社
-
5) Wilson BA, Baddeley A, Evans JJ, et al:Errorless learning in the rehabilitation of memory impaired people. Neuropsychol Rehabil 4:307-326, 1994
P.166 掲載の参考文献
-
1) 長谷川幹:在宅障害者・高齢者への援助の視点, 主体性をひきだすリハビリテーション, p10, 2009, 日本医事新報社
-
1) 安井信之, 他:III. 脳出血 3-3. うつ状態に対して, 脳卒中治療ガイドライン2009[internet], http://www.jsts.gr.jp/guideline/150_151.pdf, 篠原幸人, 他 脳卒中合同ガイドライン委員会編, 日本脳卒中学会
-
2) 田島明子:障害受容再考「障害受容」から「障害との自由」へ, 2009, 三輪書店
-
3) 南雲直二:リハビリテーション心理学入門 人間性の回復をめざして(大田仁史 監修), 2002, 荘道社
-
4) 齊藤 勇:第3章 欲求と動機の心理. イラストレート心理学入門 第2版, p55, 2010, 誠信書房
-
5) 渡辺俊之, 本田哲三:リハビリテーション患者の心理とケア, 2000, 医学書院
-
6) 特集リハビリテーション患者とうつ, J Clin Rehabil 14(8):701-720, 2005
P.178 掲載の参考文献
-
1) 大川弥生:介護保険サービスとリハビリテーション, p20, 2004, 中央法規出版
-
1) 大川弥生:介護保険サービスとリハビリテーション, 2004, 中央法規出版
-
2) 大川弥生:新しいリハビリテーション 人間「復権」への挑戦, 2004, 講談社現代新書
-
2) 鎌倉矩子:高次脳機能障害の作業療法, pp474-475, 2010, 三輪書店
-
3) カナダ作業療法士協会:作業療法の視点 作業ができるということ(吉川ひろみ 監訳), 2008, 大学教育出版
-
4) 日本作業療法士協会:"作業"の捉え方と評価・支援技術 生活行為の自律に向けたマネジメント, 2011, 医歯薬出版
P.189 掲載の参考文献
-
1) 厚生労働省, 医療保険及び介護保険におけるリハビリテーションの見直し及び連携の強化について, http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1a06.pdf
-
2) 回復期リハビリテーション病棟協会 編:回復期リハビリテーション病棟の現状と課題に関する調査報告書(2012年版), 2013, 回復期リハビリテーション病棟協会
-
3) 全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会 編:回復期リハビリテーション病棟の現状と課題に関する調査報告書(2011年版), 2012, 回復期リハビリテーション病棟協会
-
4) 厚生労働省保険局:第7部 リハビリテーション, 医科点数表の解釈 平成14年4月版, p328, 2014, 社会保険研究所
P.192 掲載の参考文献
-
1) 篠田雄一:住みやすさへの支援 住環境調整における住みやすさへの配慮, 作業療法ジャーナル 39(7):689-694, 2005
P.206 掲載の参考文献
-
1) 日本リハビリテーション病院・施設協会:回復期リハビリテーション病棟 第2報, 全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会 編, 2010, 三輪書店
P.209 掲載の参考文献
-
1) 大川弥生:「よくする介護」を実践するためのICFの理解と活用 目標指向的介護に立って, 2009, 中央法規出版