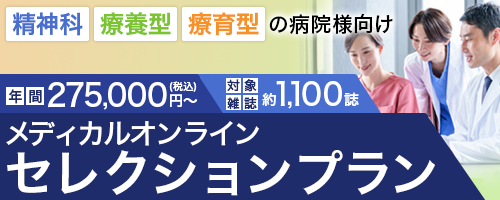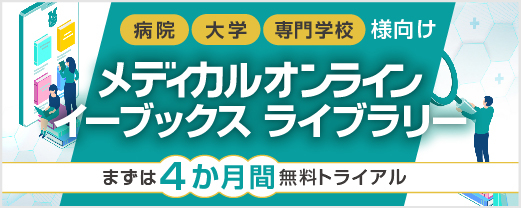アブストラクト
| Title | 臨床での脳画像のみかた |
|---|---|
| Subtitle | 講座 |
| Authors | 皆方伸1,7), 伊藤優也2,7), 佐藤孝憲3,7), 近藤友加里4,7), 佐藤久範5,7), 吉田宜明5,7), 町田陽一朗6,7), 杉山経幸5,7), 福原隆志3,7) |
| Authors (kana) | |
| Organization | 1)秋田大学医学部附属病院リハビリテーション部, 2)秋田県立循環器・脳脊髄センター, 3)中通リハビリテーション病院, 4)中通総合病院, 5)御野場病院, 6)あをによしリハビリ脳神経外科クリニック, 7)秋田県理学療法士会 神経理学療法研究班 |
| Journal | 秋田理学療法 |
| Volume | 28 |
| Number | 1 |
| Page | 21-32 |
| Year/Month | 2021 / |
| Article | 報告 |
| Publisher | 秋田県理学療法士会 |
| Abstract | 「1. 総論(皆方 伸)」「1)はじめに」脳卒中患者への理学療法を実践する上で, 画像情報を活用することは一般的となった. その要因には, 診療録が電子化されて画像を読影する機会が身近になったことが挙げられる. 加えて, 令和2年4月から適用された理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドラインでは, 理学療法評価学の教育内容の中に, 「医用画像の評価を含む」と新たに明記され, 今後は画像情報のより積極的な活用が求められる. 脳卒中患者を対象とした脳画像を用いた研究には, functional MRI(magnetic resonance imaging:核磁気共鳴画像)や拡散テンソル画像を用いたfiber tractographyなど一般臨床では取得しない方法が用いられることが多い. しかし, 大切にしたいことは一般臨床で得られる画像情報を「普通」に活用することである. そのため, 本稿では脳梗塞患者を対象にしたMRI画像の基本的な活用方法を紹介する. |
| Practice | 医療技術 |
| Keywords |
- 全文ダウンロード: 従量制、基本料金制の方共に770円(税込) です。
参考文献
- 1) 理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則の一部を改正する省令. http://www.japanpt.or.jp/upload/japanpt/obj/files/aboutpt/03_shiteikisokusyourei-181005.pdf (2020年10月7日引用)
- 2) Baird AE, Benfield A, Schlaug G, et al.: Enlargement of human cerebral ischemic lesion volumes measured by diffusion-weighted magnetic resonance imaging. Ann Neurol 41: 581-589, 1997
- 3) Tamura H, Hatazawa J, Toyoshima H, et al.: Detection of deoxygenation-related signal change in acute ischemic stroke patients by T2*-weighted magnetic resonance imaging. Stroke 33: 967-971, 2002
- 4) 酒井保治郎, 小宮桂治: 脳画像読影の基礎知識. 小宮桂治(編): 演習で学ぶ脳画像 読影からリハ介入まで. pp.3-49, 医歯薬出版, 東京, 2017.
- 5) 皆方伸: 脳梗塞. 高橋仁美(編): 病態からみた理学療法 内科編. pp.146-173, 中山書店, 東京, 2018.
残りの24件を表示する
- 6) 手塚純一. 画像からみた脳の障害と可能性. 原寛美, 吉尾雅春(編): 脳卒中理学療法の理論と技術. pp.300-317, メジカルビュー社, 東京. 2013.
- 1) 原寛美, 吉尾雅春: 脳卒中理学療法の理論と技術 改訂第2版. pp.101-102, メジカルビュー社, 東京, 2016.
- 2) 山内博: 血行力学的脳虚血と選択的神経細胞障害: PETによる検討. 脳循環代謝 19: 120-123. 2008.
- 3) Heilman KM, Watson RT, Valenstein E: Neglect and related disorders, 3rd ed, Heilman KM, Valenstein E (eds): Clinical Neuropsychology. pp.279-336. Oxford University Press, New York, 1993.
- 4) Vallar G, Perani D: The anatomy of unilateral after right-hemisphere stroke lesions. A clinical/CT-scan correlation study in man. Neuropsychologia 24: 609-622, 1986.
- 5) Committeri G, Pitzalis S, Galati G, et al.: Neural bases of personal and extrapersonal neglect in humans. Brain 130 (pt2): 431-41, 2007,
- 6) Bartolomeo P, Thiebaut de Schotten M, Doricchi F: Left unilateral neglect as a disconnection syndrome. Cereb Cortex 17: 2479-2490, 2007.
- 7) 西平賀昭, 大槻立志: 運動と高次脳機能. pp.84-95, 杏林書院, 東京, 2005.
- 8) 丹治順: 頭頂連合野と運動前野はなにをしているのか? -その機能的役割について- 理学療法学 40(8): 641-648. 2013.
- 9) 中嶋理帆, 中田光俊: 右前頭葉の高次脳機能のネットワーク. Jounal of Wellness and Health Care Vol.43(1): 1-9, 2019.
- 10) 石合純夫: 半側空間無視の発現機序と責任病巣: MB Med Reha(129): 1-9, 2011.
- 11) Corbetta M, Patel G, Shulman GL: The reorienting system of the human brain: From environmental to theory of mind. Neuron 58(3): 306-324, 2008.
- 12) Corbetta M, Shulman GL: Spatial neglect and attention networks: Annu Rev Neurosci 34: 569-599, 2011.
- 13) 石合純夫: 高次脳機能障害学 第2版. pp163-170, 医歯薬出版株式会社, 東京, 2012.
- 14) 服部高明, 石合純夫: 半側空間無視における白質障害の検討. 高次脳機能研究 31(1): 79, 2011.
- 15) Doricchi F, Tomaiuolo F: The anatomy of neglect without hemianopia: a key role for parietal-frontal disconnection? Neuroreport 14(17): 2239-2243, 2003.
- 16) Donnan GA, Baron JC, Davis SM, et al.: The ischemic penumbra. In Donnan GA, Baron JC, Davis SM, Sharp FR(eds): Overview, definition, and criteria. pp.7-20. Informa Healthcare USA, New York, 2007.
- 1) 阿部浩明, 近藤健男, 出江紳一: 脳卒中後のpusher syndrome -出現率と半球間差異-. 理学療法学 41(8): 544-551, 2014.
- 2) 網本和: Pusher現象例の基礎と臨床. 理学療法学 29(3): 75-78, 2002.
- 3) 阿部浩明, 近藤健男, 出江紳一: Contraversive pushingを呈した脳卒中例の責任病巣と経過. 理学療法学 36(2): 86-87, 2009.
- 4) 嘉戸直樹: 視床の機能とその臨床応用. 関西理学 6: 47-49, 2006.
- 5) 花川隆: 前庭・平衡機能のイメージング研究の現状. Equilibrium Research 71(2): 115-119, 2012.
- 6) 菊池正弘, 内藤泰: 画像検査で脳を探るfMRI(functional MRI: 磁気共鳴機能画像法)前庭情報と空間識の皮質情報処理機構 -fMRIによる知見-. Equilibrium Research 69(2): 66-75, 2010.
- 7) Karnath HO, Ferber S, Dichgans J: The origin of contraversive pushing: evidence for a second graviceptive system in humans. Neurology 55(9): 1298-1304, 2000.